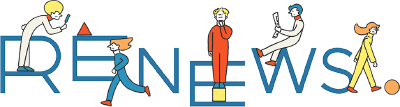コロナ禍に喘ぐバー業界の変革力 ニューノーマルを作る南雲氏の思い
▷関連記事:「地方創生」5年の成果 脱・東京一極集中、アフターコロナへの期待
「営業は午後10時まで」——。新型コロナウイルスの感染者の急増に伴い、東京都は再び飲食店に営業時間の短縮要請を出した。8月3日から31日まで酒類を提供する都内すべての店が対象だ。またか……、と悲嘆に暮れる店主も多い。
コロナ禍において、飲食店、とりわけ酒類を提供する居酒屋などは窮地に立たれさた。中でも、ほぼ酒類を取り扱う「バー」業態への影響は絶大だった。
4月に全国で緊急事態宣言が出されたとき、レストランや居酒屋はテイクアウト営業に切り替えたり、新たにデリバリーを始めたりして何とか難をしのいだところも多い。しかし、酒類が唯一の商品と言っていいバーはそうはいかない。もともとカクテルをテイクアウトする文化はなく、デリバリーへの対応もできなかった。果汁や炭酸水といった「他物」と酒類を混ぜ合わせて宅配・通信販売する行為は「酒造」と見なされ、免許が必要となるためだ。
バーの主戦場となる時間帯が来る前の午後8時に店を閉めるのであれば、開けないほうがマシと、多くのバーが休業を余儀なくされた。
そんな中、バー業界全体の生き残りをかけ、立ち上がった男がいる。日本を代表するバーテンダーであり、5店舗のバーを運営するスピリッツ&シェアリングCEOの南雲主于三(しゅうぞう)氏だ。
酒類にまつわる難解な法律
「全国のBarが存続出来るようCocktail Deliveryの認可を求めます!」
4月11日、署名サイト「change.org」でカクテルデリバリー認可の署名運動が始まった。この発起人が南雲氏だ。
南雲氏は「ミクソロジー」の第一人者としても知られる。ミクソロジーとは、フルーツや野菜、ハーブ、スパイスなどの素材を使ってカクテルを作る手法のことで、「mix(混ぜる)」と「logist(学者)」を組み合わせた欧米発の造語。南雲氏のバーではさらに遠心分離機やスモークガン、液体窒素などを使用し、斬新なカクテルを生み出している。常に最先端を走りながら、バー業界の発展に心血を注いできた。

スピリッツ&シェアリングCEOの南雲主于三氏。日本を代表するバーテンダーの一人だ
そんな南雲氏が署名活動に至る経緯を理解するには、少々難解な酒にまつわる法律を知る必要がある。
そもそも、おかずや弁当と違い、酒類を「販売」するためには、販売に際する「酒類小売業免許」が必要となる。酒店は皆、取得済みだが、店舗で酒類を「提供」する居酒屋などは免許を必要としない。ところが、テイクアウト営業に切り替え、弁当とともに酒類のテイクアウトを始めるとなると事情が異なる。テイクアウトに業態変換した途端に、「酒類を販売する行為」と見なされ、免許が必要となるのだ。
そこで、酒造組合や酒造会社が中心となって「酒税法」を管轄する国税庁に特例措置を働きかけた。これを受け、国税庁は4月9日、期限付酒類小売業免許の付与を発表。許可通知から6カ月間限定だが、飲食店は簡単な届け出によって酒類のテイクアウト販売ができるようになった。すぐに税務署に認可申請が殺到し、申請期限日の6月30日までに認可数は全国で2万5638件に上っている。
しかし、この特例措置で販売できる酒は、日本酒やウイスキーなど、店舗にある酒類をそのまま、小瓶などの容器に注ぐ「量り売り」に限る。あらかじめ、まとまった量を小瓶などに詰め替えて準備しておく場合は、「酒類の詰替え届出書」を所轄の税務署に提出する必要がある。酒類を混ぜ合わせたカクテルを販売するというのは、もっとハードルが高い。
前述のとおり、酒類と何かを混ぜ合わせてカクテルを作り、それを販売するためには、酒類メーカーなどが取得している「酒類製造免許」を得る必要がある。街中のバーが酒造免許を取得するのは容易なことではない。
2日で2000人以上の署名
法を犯すわけにはいかない。いつ自粛要請が終わるか分からない事態のために免許を取得するのも非現実的だ。だからといって、何もしないわけにもいかない。そこで、南雲氏は一計を案じた。
期限付酒類小売業免許の特例措置が設けられたことを受け、店頭で作ったカクテルをその場で持ち帰ってもらう「テイクアウト販売」ならいけるのではないか。酒類や混ぜる素材を材料別に容器に詰め替えてセット販売すれば「デリバリー販売」も可能ではないか——。
すぐに税務署に問い合わせたところ、「カクテルのテイクアウトもデリバリーもNGだという回答だった」(南雲氏)という。しかし、南雲氏は諦めなかった。バー業界の窮状をもっと多くの人たちに知ってもらえれば、この局面を打開できるかもしれないと、change.orgで署名を集め始めたというわけだ。
要望は、シンプルだ。営業許可を持っている店舗内で調合されたカクテルを、瓶または真空パックなど密閉容器に入れて、テイクアウト販売またはデリバリー可能にしたい。酒税法そのものを変えるのは短期間では難しいため、非常事態として、期限付で特例として認めてほしいというものだった。
具体的には、まず、それぞれのバーが期限付酒類小売業免許を取得することが前提となる。その上で、所轄税務署の許可を得るために「詰め替え届け出」や、酒類の仕入れ数や販売数量などを証明する「帳簿の作成と提出」を義務付ける。デリバリーは「2都道府県以内」の販売に限る。これらを1年の期限付きで認可してほしいといった要望である。
この時のことを、南雲氏はこう振り返る。
「売り物がないバーにとっては、店を閉める以外の方法はありませんでした。しかし、これから本格的なコロナ不況が来るのに、無策ではただつぶれるしか道はないのです。それは回避しなくてはなりません。だから、少しでも売り上げを出すために、カクテルのテイクアウトやデリバリーを認めてほしい。1年間の猶予があれば、その間に経営の土台を作り直せるという思いでした」
この呼びかけに業界の錚々たるメンツが賛同した。パレスホテル東京やザ・ペニンシュラ東京、ザ・リッツ・カールトン京都といった一流ホテルで腕を振るうバーテンダーから、酒類ジャーナリスト、アサヒビールやサッポロビールといった大手酒類メーカーの社員まで、change.orgの署名ページには147人の賛同者が連なった。
これに世の中も敏感に反応した。集まった署名はわずか2日で2000人を超え、8月13日時点で3491人の署名が集まっている。
「同業者やバーファンなど皆さんにも危機感があり、何かをブレークスルーする動きに賛同する流れがありました。それがここまでの署名の数につながったのだと思います。本当にありがたい気持ちでした」。南雲氏はこう相好を崩す。
国税庁酒税課に直談判
全国のバー業界、そしてバーのファンを味方につけた南雲氏は、この実績を引っさげ、国税庁にかけあう。
4月15日、嘆願書を持参した南雲氏は酒税課の担当官と会い、バー業界の課題を解決するための方法について話し合った。ただし、署名活動での要望通り、カクテルをそのまま瓶などに詰めてデリバリーで販売するのは、どうしても酒税法を改正しなければならない。それだと国税庁の範疇を超え、財務省での検討、そして国会の審議が必要となるという。コロナ禍の危機は目の前にあるのだ。そこまでの時間的猶予はないため、南雲氏はあくまで既存の法律の中での拡大解釈を訴え、落としどころを見出そうとした。
救いだったのは国税庁の担当者も理解を示してくれたことだ。
膝を突き合わせ議論をする中で、店で提供する範疇ならば、たとえカクテルが入った容器を顧客が持ち帰っても、それは顧客の判断によるものだという「見解」を得た。例えば、その場ですぐに飲めるようにプラスチック容器でカクテルを提供した場合であれば、顧客が店外に持ち出し、たとえ家に持って帰ったとしても、直ちに「販売行為」だとは見なされない、という見方だ。これによって、条件付きではあるが、カクテルのテイクアウト販売の道が拓けた。
一方で、難易度の高いデリバリー販売についても光明を見出だせた。協議を進める中で、南雲氏が当初思い描いていたように、混和した状態ではなく、材料別に容器を分けてセットにし、カクテルの「キット販売」をするぶんには問題がない、という見解を得たのだ。
デリバリーに関しては衛生面もかかわってくる。国税庁だけでなく保健所とも確認を取りながら調整を進めた結果、店側が所轄税務署に容器への詰め替えを行う2日前までに「酒類の詰替え届出書」を提出し、製造場所(詰め替え場所)や事業者名などを表示すれば、カクテルキットのデリバリー販売も可能だという結論に至った。
こうして、カクテルのテイクアウト販売およびデリバリー販売に関するルールが整理され、4月20日、国税庁から正式な文書が発表された。
この知らせに全国のバー関係者やカクテルファンは喜んだ。奔走した南雲氏はこう語る。
「酒造組合などが動いてくれて期限付酒類小売業免許を実現したことが大きいです。私はその上で、できること、できないことの情報を整理しただけです。ただ、こうした厳しい状況の中で、最初の一歩を踏み出す、ゼロからイチを作るのは勇気とタイミングが必要で、自分自身、常にそれを肝に命じています」
全国のバーにテイクアウト販売が広がる
さっそく、南雲氏は自身の店舗で、「ブラックビアード(税込1980円)」や、「ジャンマリファリナ(税込1650円)」などのテイクアウト販売を始めた。
同時に、デリバリー用のカクテルキットも新たに開発。たとえば、「ほうじ茶ラムマンハッタン4杯セット(税込5280円)」は、ラム酒の「ロンサカパ」やベルモットの「カルパノ アンティカ フォーミュラ」などをセットにしたもの。マンハッタンに深煎りほうじ茶を漬け込んで作るアレンジカクテルだ。こうしたカクテルは市販品ではもちろんのこと、一般の消費者が家で作れるようなものではない。バーならではの価値をパックに詰めたと言える。

「ブラックビアード」のカクテルキット
とはいえ、客自身でカクテルを仕上げるのはハードルが高いように思える。そこで極力、工程を簡単にするよう工夫し、わかりやすい説明書もつけた。さらに、初心者でも完成できるようYouTubeに動画をアップするという念の入れようだ。
実績は上々。休業や時短営業の損失を補うまではいかないが、連日のようにオーダーが入り、SNSでは南雲氏に喜びや感謝を伝える客の声も見られた。バーが自力で収益源を確保する新たな道は、南雲氏の店舗だけではなく、全国のバーの助けにもなっている。
横浜市にあるダイニングバー「ニュージャック」では、4月下旬から材料を容器に詰めたカクテルキットを作り、看板メニューであるジントニックを販売している。店長の中村純氏はバー業界のSNSコミュニティーでカクテルのテイクアウトができることを知り、すぐさま実行に移した。単にカクテルキットを売るだけでなく、美味しい飲み方などを提案するオリジナルの動画も作り、Facebookにアップした。「自粛モードの中、新しい取り組みができるようになったことで、スタッフのモチベーションも高まり、活気付きました」。と中村店長は力を込める。
一般酒類小売業免許の取得で販路拡大へ
南雲氏の戦いはこれで終わらない。そもそも、今回の特例措置は「期限付き」であり、年内には、少なくとも、デリバリー販売ができなくなってしまう。テイクアウト販売に関しても、新たな見解が出て、中止せざるを得なくなる可能性もある。
さらに、仮にコロナ禍が収束したとしても、自粛の反動から消費が爆発する「リベンジ消費」は起きにくいと南雲氏は考えている。人々に植えつけられたコロナの恐怖心はすぐには消えないからだ。南雲氏は言う。
「売り上げは戻ってもコロナ前の7割程度ではないでしょうか。隣の客と密着するような飲み屋にすぐ行きたいと思いますか。密閉された個室で飲みたいと思いますか。人々の価値観は大きく変わりました。これを取り戻すのは時間がかかるし、店側も席数を減らす、換気を良くするなどの工夫をしないといけません。路面店ならまだいいですが、空中店舗や地下店舗だとより経営が厳しくなるかもしれません。だからこそ、新しいアイデアが必要です」
そのための新しいアイデアはいくつか持ち合わせている。1つが、正式な「一般酒類小売業免許」の取得だ。期限付酒類小売業免許だと店舗在庫や既存取引先から仕入れた酒類の販売に限るが、一般酒類小売業免許であれば卸売業者や製造業者から仕入れて、幅広いラインナップを消費者に販売できるようになる。
これまで、バーが小売業免許を取るという発想はなかった。しかし、この第2波が終息したとして、3波、4波が冬に到来する可能性もある。人類がコロナ禍に打ち勝ったとしても、また新たなウイルスがいつか流行するかもしれない。その転ばぬ先の杖として、バーが一般酒類小売業免許を持つ、ということに南雲氏は意味を感じている。
「免許取得を進めていますが、今のところ特に問題は感じていません。場所を確保し、卸業者と取引を決め、所轄の税務署に申請すれば良いのです。今はネット販売だけの酒販店もあるので、実店舗を作る必要もありません。自由にお酒が販売できる状態は整っているのです」
免許を取得することでバー経営の改革を進めようとする南雲氏の行動は、全国の同業者に挑戦するきっかけや勇気を与えるだろう。
バーテンダーの知恵を生かした商品開発
さらに南雲氏は、メーカーなどとコラボレーションした商品開発にも乗り出した。
リキュールの製造免許を持つJCCエージェントと組み、南雲氏が監修したボトルカクテル商品「ブリティッシュ ネグローニ」を6月に発売。オンラインで購入できるようにした。これは、たとえば、ラーメン屋とコラボしたカップ麺がコンビニなどに置いてあるのと同じ発想だ。
「カクテルも、バーとコラボした商品があってもいい。商品の監修であれば、バーテンダーの知恵や技術をそのまま生かすことができます。これは私だけの専売特許ではなく、多くのバーテンダーにとっても新しい収益源になるはずです」。南雲氏はそう意気込む。
現に、南雲氏に続けと、酒造メーカーとコラボレーションして商品開発を実現したバーテンダーも出てきた。札幌の有名店「the bar nano gould.」のオーナーバーテンダーである富田健一氏が焼酎蔵元の小正醸造とコラボしたボトルカクテル「#02 FRAGRANT PARISIEN」も、その一つである。
アイデアやスキルを積極的に開示
南雲氏のこうした新たな取り組みは、コロナ禍で自分だけが生き残るためにやっているわけでは決してない。バー業界の多くの関係者が苦境に喘ぎ、一寸先は闇である状況の中、自らがリスクをとり、率先してやることで、知見や経験が広がり、業界全体の底上げにつながれば本望だと考えている。
カクテルのテイクアウト販売やデリバリーに向けて国税庁などに直談判し、仲間のためにルールを明確にしたことが何よりの証拠。そもそも、南雲氏はコロナ禍以前から、バー業界のためを思い、公益的な活動をしていた。
その一つが、16年に立ち上げたバー業界のオンラインコミュニティー「バーテンダージャーナル」。現在、国内外1200人が参加し、バーテンダー向けのイベントや求人、不動産物件、リカー情報などを日々シェアしている。このコミュニティーを通じ、南雲氏は自らのアイデアを開示して、バーに関わるスキルの伝達を惜しまない。例えば、カクテルづくりのための新しい機材を日本でいち早く導入すれば、そのレクチャーを全国のバーで行なってきた。
もう一つ、南雲氏はバー業界全体の発展に向け、大きなアイデアを以前から温めていた。「オンラインアカデミー」構想である。
トップレベルのバーテンダーを育成するオンラインスクールを立ち上げる計画。国内はもとより、海外でもバー業界に特化したものは類を見ないという。
なぜ学校なのか。これまで日本には基礎講座中心のバーテンダー向け専門学校くらいしかなく、それ以上のことは独学しかなかった。それがバーテンダーのスキルアップの障壁となっていた。そこで、現場で生かせる応用技術や、世界のバーの最新トレンド、さらにはバーの経営戦略なども習得できる学校を目指す。
コロナ禍でバー業界の変革は加速
「現状の専門学校が小学校とするならば、MBAのようなスクールを作りたい」とする南雲氏は、こう続ける。「昔と比べて日本でもバーの社会的な地位は高まっていますが、まだまだ働く環境をはじめ課題は多いです。そうした状況を少しでも変えていきたいし、常にイノベーティブなことを業界全体で取り組んでいれば、次に入ってくる人たちの安心材料にもなるはずです」。
今回のコロナ禍によって、最も打撃が大きかった業種の一つ、バー業界は、力強く未来を見据えている。むしろ、変革の速度をコロナ禍以前よりも加速させているのかもしれない。
もちろん、コロナ禍などないほうが良いに決まっている。だが、避けられないのであれば、自らが変革するチャンスと捉え、新たな境地へ進化していくべきだ。環境に適応できない者は廃れるのが世の常。悲嘆に暮れず、変革に挑戦するバー業界に学ぶことは多い。
▷シリーズ:アフターコロナ時代を生き抜くためには?
-
地方の企業、行政、地域活性化などの取材を通じた専門性を生かし、「地方創生の推進」に取り組む。1979年生まれ。神奈川県出身。慶應義塾大学環境情報学部卒業、同大学院政策・メディア研究科修了。ニュースサイト「ITmedia」、フリーランスを経て、現在に至る。 |伏見学(ふしみ・まなぶ)