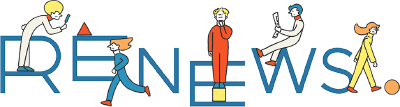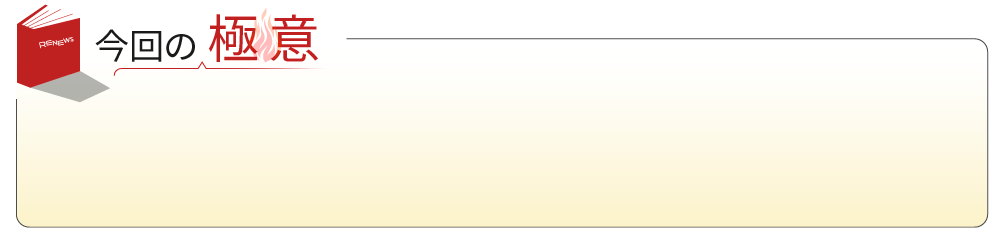日本一小さな村に学ぶ移住者の増やし方 富山・舟橋村の子育て支援
筆者が暮らす富山県中新川郡舟橋村は、面積3.47平方キロメートルの「日本一小さな村」である。地方自治体の半数以上が人口減に喘ぐ中、舟橋村は30年で人口を2倍以上に増やした。1990年時点で1500人弱だった人口は、2020年6月現在で3185人に。特に15歳未満の年少人口指数が高いことが特徴で、10年度には21.8%となり、日本一になったほどである。
なぜ人口が増大したのか。まず、村は「子育てにやさしいまち」を掲げている。かつ、富山市街地からクルマや鉄道で20分というアクセスの良さも手伝い、近隣自治体の子育て世帯からの人気が高い。実際に移住者の大半がそうした世帯だ。彼らの多くは友人・知人などからの口コミで舟橋村を知り、村を見学して、「ここならば」と引っ越してくる。
1つのヒントがここにある。多くの地方自治体のように、東京をはじめとする大都市圏からの移住者を狙わず、お互いをよく知る近隣エリアからの移住者を求めることが、人口増の近道となっている。
ただし、これだけで人口が増えるわけではない。「移住者が多い」「子育てにやさしい」と聞いたとき、多くの方が想像するのは移住者への補助金や、子ども向けの施設・制度の充実だろう。現に移住者対策としてそのような経済面、ハード面での支援に力を入れる自治体は数多く存在する。
だが舟橋村には、そうした定石が当てはまらない。実際に、村に住む子育て世帯の親に聞くと、「補助や制度が充実しているとは思わない」という声が多く挙がる。ではなぜ、舟橋村は移住者が増え続けているのだろうか。その答えは、「関わりしろ」を仕組み化したことに尽きる。
▷関連記事:「地方創生」5年の成果 脱・東京一極集中、アフターコロナへの期待
子育て支援センターの仕組み化
関わりしろとは、自分がその地域やコミュニティーにかかわることができそうな余白のことを言う。「ソトコト」の指出一正編集長が提唱する言葉で、東京をはじめとする大都市と比べてローカルには隙が多く、色々な人たちがかかわることのできる余地が多いのだという。例えば舟橋村で筆者は、住民有志のまちづくり活動に誘われ、イベントを手伝ったり、農業団体のパッケージデザインに携わったりした経験がある。これは東京のような大都会では「仕事」としてかかわるものである。
しかしながら、単に関わりしろがあるだけでは不十分。関わりしろがあったとしても、その存在を移住者が知らなければ意味がない。また、移住者が心の中で「他の住民とつながりたい」「地域活動に参加したい」と思っていても、多くの場合は逡巡して積極的になれずに終わってしまうだろう。
だが、舟橋村は違う。地域活性に対してさほど意識が高くない移住者や村外の人でも、村に自然とかかわれるような仕組みや仕掛け、サポート体制が確立されている。そうして村に溶け込んでいった移住者が、新たな移住者の呼び水にもなっている。
この仕組みが端的に表れているのが、未就学児童の親子が集う「子育て支援センター」だ。

「子育て支援センター」は朝から多くの親子が利用している
子育て支援センターとは、主に乳幼児とその親が自由に利用できる公営のフリースペース。舟橋村は富山県内で唯一、同センターを持たない自治体だったが、15年4月、村役場内に開設された。開所からの延べ利用者数は8000人を超えているが、じつに利用登録者の85%もの人が村外の住民である。
中にはクルマで1時間もかけて域外からやってくる親子もいる。当然、近隣自治体にも子育て支援センターは存在するし、舟橋村のハード設備自体が他と比べて優れているわけでもない。それでもわざわざやって来るのは、住民であろうが、村外の人間だろうが関係なく、誰もが施設内の活動にかかわりやすくするための仕組みが意識的に作られているからである。
その仕組みにおいて、スタッフが重要な役割を果たしている。舟橋村の子育て支援センターのスタッフは、保育士歴が1年未満、あるいは保育士の資格を持たない者がほとんどであることが大きな特徴だ。
一般的な子育て支援センターでは、ベテランの保育士がきっちりと子どもの面倒を見ている。言わば「正解のある場づくり」が当たり前だった。しかし、ベテランの保育士はどうしても「先生」になりがちで、保護者に教える構図になってしまい、利用者の関与を許さない。舟橋村でも、子育て支援センターの立ち上げ当初はベテランの保育士に任せていた。保護者に対して一方的なコミュニケーションになってしまい、両者に溝が生じていたという。
そこで2年目から、あえて若い保育士を中心とした体制へ変更。保育士たちの役割を先生ではなく、保護者と同じ目線の「仲間」とし、利用者と気軽にコミュニケーションを取るようにしたのだ。その上で、スタッフは保護者同士をつなげる「コーディネーター」としての役割も担うようにした。
例えば、生後半年の子どもに関する悩みごとが保護者からあった場合、スタッフ自身が回答しようとはしない。乳幼児を持つ別のセンター利用者に声を掛け、「〇〇ちゃんが半年のときってどうしてた?」と水を向け、保護者同士のコミュニケーションを誘発していく。それを機に双方は顔見知りとなり、関係性が発展していくことも多い。そうして、保護者同士の輪がセンターを起点にどんどんと広がっていった。
センターの担当者である舟橋村生活環境課の廣瀬美歩係長はこう語る。「利用者同士のかかわりが自然と生まれるこの“ゆるさ”が、舟橋村らしさ。他の地域から来る親御さんもその違いに驚くことが多い」。
コミュニケーションを活発にする仕掛けは枚挙に暇がない。
スタッフは、あえて利用者の面倒をすべて見ることはしない。利用者に手伝ってもらうことを前提にしているためだ。例えば、子どもの遊び道具など必要なものは自分たちで用意してもらう。子どもを連れてきた親が所要でセンターを出る際は、スタッフではなく、別の親に見守ってもらうようにしている。そうすることで、利用者同士が自然と協力し合うようになる。
さらには、利用者一人ひとりが主役となれる機会を作る仕掛けもある。こちらは、センター開催のイベントに色濃く表れている。
誰にでも活躍の場がある
他地域のセンターのイベントであれば、外から「講師」を連れて来るのが一般的だ。しかし舟橋村では、美容師の資格を持つ利用者がいれば「子どもの髪を切るコツ」を教える講座を開いたり、手芸の上手な親がワークショップを開催したりと、利用者が得意なことを生かして講師となる機会を積極的に作っている。誰にでも平等に活躍の場を用意しているのだ。
講師として前に立つことで、さらに多くの利用者たちとコミュニケーションを取ることが可能になるし、参加者たちも仲間の生き生きとした姿を見て、「今度は自分もやってみたい」という前向きな気持ちを抱くようにもなる。自ら手を挙げることに億劫になっている保護者に対しては、スタッフが日ごろの会話の中でその人の特技などを見つけ、「○○さん、今度、講師をやってみたら!?」などと背中を押すようにしているという。
これら仕掛けの素地を作ったのが、子育てサークル「さくらんぼくらぶ」前代表の沙魚川(はせがわ)恵子さんだ。東京からの移住者だった沙魚川さんは03年7月、子育て中の母親などが交流できる場を作るため、同サークルを立ち上げた。そもそも子育てコミュニティーというものは村で初めてということもあり、すぐに評判となり、運営をサポートしたいという人も村外から集まるようになった。
15年4月に舟橋村に子育て支援センターができると、役場の担当者はすぐに運営をさくらんぼくらぶに依頼した。行政の施設だからといって、基本的なスタンスは変えていない。「できる人が、できることを、できる時間だけやればいい」と沙魚川さんは話す。

沙魚川恵子さん(右)。舟橋村の子育て環境を整備したと言ってもいい人物だ
会話が生まれる図書館
「子育て支援センターを利用しない人たちはどうなのか」という疑問が当然湧くだろう。関わりしろを意図的に埋め込んだハード施設は、ほかにもある。図書館だ。
舟橋村の図書館は、人々の“たまり場”。コミュニティー・スペースとしての機能が強い。住民だろうが、村外の人だろうが、移住したての新住民だろうが、とりあえずここに来る。結果、本に触れる頻度も高くなり、住民一人当たりの図書貸出冊数が33.4冊(2016年)と日本一になった。村外の利用登録者が8割を超えることも、その吸引力を物語っている。
人々が集まるのは、ハード面が充実しているからだと考えがちだろう。確かに舟橋村の図書館は駅前という好立地で、全館木製フローリングという特徴はあるが、蔵書数や種類などの中身は普通の図書館とさほど変わりはない。これも、ソフトの部分が他と圧倒的に異なる。

図書館での読み聞かせイベントの様子
「○○さん、今日は早いですね」――。高野良子館長を初めとする図書館スタッフは、一度訪れた利用者の名前を忘れないことを徹底し、とにかく利用者への「声かけ」を頻繁にしている。これにより、両者は単に「お客さん」と「サービス提供者」という関係性を超え、顔の見える間柄となる。いつしか利用者は、本を借りる用事がなくとも、会話目当てにやって来るようになるのだ。
図書館へ訪れた際、特に用事もないのに職員のほうから話しかけられた経験がある人はどれくらいいるだろうか。普通は探している本が見つからない時などに、利用者からカウンターにいる職員に声をかける。舟橋村はその逆なのである。
図書館もまた、子育て支援センターと同様、晴れ舞台を提供することで、利用者の関わりしろを意図的に作っている。例えば、図書館の一角を使い、利用者の趣味や特技を生かした作品の展示会を月1回ペースで開催しており、展示会だけで年間900人ほどの来場者を集めている。
本人自ら立候補することもあれば、高野館長が打診する場合も。この展示会という関わりしろを機に利用者同士の交流が生まれるのは想像に難くない。スタッフも展示会に参加した人の趣味などが把握できるため、次に来館した際に最適な本を推薦するなど、新たな声かけにつながる。利用者はそれに喜び、再び足を運ぶようになるという好循環が生まれている。
人口増の陰には課題も
ここまで紹介してきたように、舟橋村は多くの人たちのかかわりを作るためにいくつもの仕掛けを用意している。移住政策と言えば、補助金やハード施設の拡充に目が行きがちだが、舟橋村はそうではない。舟橋村の図書館の設計図を真似て、図書館を建設しても無意味なのである。
そして、この「意図的な関わりしろ政策」が、域外の人への格好のアピールとなり、日本一小さな村でも移住者が増え続けるという結果につながっている。
冒頭で述べたように、舟橋村には近隣自治体からの移住者が多い。その中には以前から舟橋村の子育て支援センターや図書館などを利用していた人たちが一定数いる。彼ら彼女らは村とのかかわりが強まった結果、移住してきたのである。そうした人たちの声を直接的または間接的に知り、転入してくるケースもあるという。
かくいう筆者も、18年に東京から舟橋村に移住してきた子育て世帯。仕事で初めて舟橋村を訪れた際、村人のオープンな姿勢や、誰でも入っていけそうなコミュニティーの風土に感動し、移住を決めた一人である。

小さいことが課題にもなる
一方で、舟橋村の人口増加は新たな課題をもたらす。それは「住む場所がない」ことだ。住宅用地は限られており、今後も同じペースで新規転入者を確保していくことは難しいだろう。
しかし、この村に住みたいと願う子育て世帯はまだいる。その対策として取り組んでいるのが、「子育てシェアビレッジ」の形成だ。ここでは、子育て世帯のための村営住宅を中心に、幼保一体型の子ども園や学童保育施設、村の子どもたちがクラウドファンディングを活用して実現した公園「オレンジパーク」などの施設が一帯に広がっている。各所の物理的な距離の近さを特徴に、子育て世帯同士や周辺住民が助け合えるまちづくりを推進しているのだ。単にハードを用意するだけでなく、ここでも住民の関わりしろを作り、村のコミュニティーの強化につなげていく。

舟橋村は自転車でもあっという間にぐるりと一周できてしまうほどの小ささだ
地域の持続には仕事も必要だ。新しいビジネス創出も、将来を見据え力を入れている。村内の若手農業者や飲食事業者、農業関係事業者らとともに筆者が19年から携わっている「農業ブランド化プロジェクト」もその一つ。生産現場へのIT導入促進から、かぼちゃやトマトなどの個別産品・加工品のブランド化までを通じた産業活性化に取り組んでいる。今年度は住民を巻き込んだ商品開発やオンライン・オフラインでの販路開拓にも力を入れる。
「日本一小さな村」がこれから向かうのは、ただ人口を増やし、拡大するような過去のモデルに倣うのではなく、ごく普通の住民一人ひとりが地域に関わりを持ち、「共助」していくまちだ。筆者もその一員として、支え合うまちづくりに今後も貢献していきたい。
■訂正・修正履歴
(2020/07/15 17:00)記事中、一部の表現を修正しました。
-
1984年長崎県生まれ。筑波大学大学院修士卒。戦略PRコンサルティング会社を経て、2014年にStory Design house社を共同創業後、17年より現職。企業・地域のPR/ブランド支援などに取り組む。現在は日本一小さな村として知られる富山県舟橋村と東京の二拠点生活。 |岡山史興(おかやま・ふみおき)