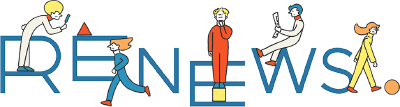沖縄資本反撃へ 宮古島・パラダイスプラン「雪塩」に学ぶ処方箋 #2
▷第1回:沖縄初の子ども食堂 県外の“ナイチャー”が貧困支援で成果(#1)
活況に沸く沖縄——。ここ数年、幾度となくこのフレーズを目にした。外国人観光客が大挙して沖縄に押しかけ、その需要を取りこぼさぬよう各地に大型商業施設が相次いでオープンした。2018年度の沖縄県内総生産(名目)は4兆5362億円と、11年連続増加の見込みだ。今後、新型コロナウイルスの影響が数字にどう現れるかは分からないが、マクロ的に見れば好景気が長らく続いていた。
ただし、目を凝らすと沖縄経済は課題が山積だ。
好調なのは観光や小売、電力、通信業界の大手企業が中心。沖縄県内企業の99.9%が中小・零細企業であり、それらは軒並み厳しい経営環境にある。沖縄県中小企業団体中央会の景気動向調査によると、企業の景況感を示す業況判断指数(DI)は20年4月現在、全業種で31カ月連続マイナス。新型コロナウイルスの影響で今年に入ってマイナス幅が急拡大した。また、東京商工リサーチの調べでは、18年の県内企業の休廃業・解散件数は375件で、調査を始めた00年以降で過去最多に。翌19年度も370件と過去2番目の多さだった。
観光や小売りに関しても、「県内企業」にとっては、決して安泰とは言えない。この領域は本土企業や外資企業の草刈り場。次々と外から企業が沖縄に乗り込んできては幅を利かしている。
例えば、沖縄本島ではホテルの建設ラッシュが続いているが、ほとんどが県外企業による経営だ。今年1月にも、那覇・国際通りのど真ん中に13階建て、総客室数260室の巨大ホテル「ホテルコレクティブ」がオープンしているが、台湾の資本である。
不動産の開発ラッシュによって建設業は潤うのではないかという見方もあるだろう。しかしながら、県内の建設会社は本土企業の下請け、孫請けが常態化しているため、実入りは少ない。
収益を吸い上げられる宮古島
沖縄の中でも、こうした外部からの煽りをもろに受けているのが宮古島である。
アジア方面からの大型クルーズ船の寄港回数が増えたことで、この10年間で観光客数は約4倍まで増加し、人口わずか5万5000人の小さな島に年間114万人が押し寄せている。ただし、その観光客が落とすお金は最終的に、県外あるいは海外の企業に吸い上げられている。クルーズ船の外国人観光客の多くは、港に着くと大型バスに乗り込み、ドン・キホーテやマックスバリュ、ヤマダ電機などを回って免税品を買い漁り、船へと戻っていく。飲食店を経営する地元関係者は「外国人が来ることは滅多にない」と話す。

宮古島と伊良部島をつなぐ伊良部大橋の開通によってリゾート開発が一気に加速した
さらには過熱するリゾート開発によって次々と外資系ホテルが進出。地場の宿泊施設が太刀打ちできるはずもなく、地元資本の弱体化は加速する一方だ。この影響は住民の暮らしにも及ぶ。
バブルによる地価高騰で土地を買うことが年々難しくなっている上に、建設業者やホテル従業員が急増したことで賃貸空き物件が不足し、島内で引っ越しができない人も出てきている。新型コロナウイルスの影響によって鈍化しているものの、開発は当面続く見込みである。
県外企業と競い合う力がないために、下請けにならざるを得ない、あるいは、ただ指をくわえて見ているしかない。このままでは沖縄はどんどん貧しくなる。抜け出すためには沖縄の経済的自立が不可欠だ。つまり、沖縄の地場資本が強くならない限り、経済的な苦境から抜け出すことはできない。その課題に並々ならぬ情熱を燃やして立ち向かう会社が宮古島にある。
沖縄のために上場したい
平日の昼下がり、宮古島の市街地から少し外れた場所に、ひときわ賑わいを見せる物産店があった。
駐車場にはひっきりなしにクルマが出入りしている。店の中は島内で収穫されたメロンやゴーヤーを手に取る若い女性、土産用にお菓子を物色する外国人、カフェスペースで和気あいあいとソーキそばをすする地元の年配夫婦などでごった返していた。

宮古島のものづくりを情報発信する場としてパラダイスプランが2013年に開業した「島の駅みやこ」。400を超える生産者の商品が並んでいて、宮古島を存分に味わえる。観光客だけでなく地元住民も日常的に利用する
この店の名前は「島の駅みやこ」。コンビニ2店舗分ほどの売り場に所狭しと色とりどりの商品が並んでいる。ほとんどが宮古島で作られたものだ。年間の来客数は29万人を超える。
椅子に腰掛けていると、客と談笑していた男性が向こうからやってきた。「すみません、お待たせしました。知り合いに捕まっちゃって」と頬を緩ませる。島の駅みやこを運営するパラダイスプランの西里長治社長(52)である。押し出しが良く、快活に見える。それもそのはず。趣味はランニングで、年に数回マラソンレースに出場するスポーツマンだ。
パラダイスプランという社名に聞き覚えがなくても、主力商品である「宮古島の雪塩」を知る人は多いだろう。

「宮古島の雪塩」の年間生産量は約167トンに上る
同社は塩の製造や販売に加えて、島の駅みやこのような実店舗も運営している。18年度の売上高は26億1926万円、経常利益は1億7679万円。00年度から売り上げは26倍も伸びた。社員数は約300人。沖縄資本を代表する1社である。
「いやいや、まだまだですよ。上場するためには、もっと頑張らなくては」と西里社長の鼻息は荒い。もし上場となれば、宮古島の会社としては史上初、日本の離島でも前例がない。
なぜ上場したいのか。そう問うと、西里社長は即答する。
「僕は沖縄の企業のお手本になりたいと思ってるんです。西里のところ(パラダイスプラン)でも上場できるんだったら、俺たちもやってやろう。そう奮起してもらいたいんです」

パラダイスプランの西里長治社長。沖縄のために何をすべきかを思案する日々が続いている
“無法地帯”の沖縄
西里社長がそれほどまでに成長を求める背景には、沖縄経済への危機感がある。
「沖縄は自然豊かで非常に魅力的な土地である反面、ビジネスにおいては“無法地帯”。外資企業や本土の大手企業などが次々と入ってきています。そうするとカネもノウハウも人材もない地元の会社は到底敵いません。特に観光のような設備型の産業は勝ち目がない。よその地域と同じような風景が、沖縄でもでき上がっているのです」
本来ならば地域経済のけん引役となる製造業も沖縄ではなかなか育たない。沖縄の産業構造を見ると8割以上が第3次産業で、製造業はわずか4%足らず。他県と比較しても圧倒的に小さい。これは「輸送コスト」の問題が大きく関係する。ものを作っても簡単には売れない。
「沖縄の企業がたとえ良いものを作ったとしても、そこから東京などの大都市圏までは長い輸送距離があります。沖縄で消費される、あるいは沖縄で購入することに意味のある商品しか対抗できないのが現実です」
その商品とは、工業製品ではなく、農作物や水産物の加工品。パラダイスプランはそこに勝機を見出した。
ただし、言うは易く行うは難し。沖縄で購入することに意味のある農水産物の加工品を作れば上手くいくわけではない。
多くの沖縄企業が劣勢に立たされる中、小さな離島で生まれたパラダイスプランが躍進を続ける背景を探ると、いくつかの「心がけ」がそこにはあった。他の沖縄企業からすれば、それは「学び」である。
同業他社の商品も売る
まず、パラダイスプランは、作るだけではなく、「売り方」にまで神経を注いでいる。
「沖縄の企業に足りないのは、直接、モノを売る場所の確保です。そういう仕組みが作りきれていません」。そう指摘する西里社長によると、良いものを作っている会社は沖縄に多いが、ほとんどが流通へ流す「卸売」で終わるため、沖縄企業は収益性が低いのだという。船井総合研究所の調査では、卸売チャネルの営業利益率は平均3~5%、直接販売チャネルは15~20%というデータもある。
しかしパラダイスプランは違う。直営店舗を10店以上運営するなどして、直売事業の拡大に積極的だ。これだけの規模の店舗展開は沖縄のメーカーでは珍しい。「僕らはずっと製造直売のスタイルを貫いてきました。そして商品を作るよりも先に売り場作りを優先しています。それが事業の成長にも結び付いているのです」と西里社長は強調する。
とはいえ、パラダイスプランも最初は卸売中心のビジネスモデルからスタートした。そこから直売にシフトしたきっかけは、「顧客対応の価値」に気付いたことだった。

雪塩ミュージアム
宮古島の北端にある同社の製塩所は、「雪塩ミュージアム」という観光施設を併設する。以前、普通の工場だった製塩所の中に、一般の人たちが勝手に入り込んでしまう状況に頭を抱えていた。そこで02年10月、雪塩ミュージアムと銘打ち、きちんとガイドをつけて雪塩の製法などを紹介するようにした。併せて販売所も作ってみたところ、雪塩が飛ぶように売れた。商品のことを丁寧に説明すれば顧客は買ってくれるし、何より、スーパーマーケットなどに卸すよりも2倍も3倍も収益性が高くなることを身を以て体験した。今では同社売上高の10%を雪塩ミュージアムが稼ぎ出している。同社が直売、小売りビジネスに力を入れ始めたのはここからだ。
一例が、沖縄と東京で計6店鋪を展開する塩の専門店「塩屋(まーすやー)」。雪塩の直売ルート拡大を目指して開業したが、自社の商品だけを扱っているわけではない。世界中から約650種類もの塩を取り寄せ、「塩のテーマパーク」と言わんばかりの演出をしている。西里社長は言う。
「他社の塩も全部ひっくるめて販売すれば、『専門店』として打ち出せます。目先の損得勘定だけでなく、どうしたら雪塩がもっと売れるような場所になるのかを考えました」
専門店と謳うからには、店員の塩に対する深い知識が必要である。そこで「ソルトソムリエ」という塩の専門家制度を独自に確立し、スタッフの育成を強化した。これによって顧客に塩を選ぶ基準を提案できるようになり、「あそこの店に行けば自分に合う塩が見つかる」といった評判にもつながった。
「モノを作るよりも売り場を作れ!」
経営の神様、京セラの稲盛和夫名誉会長との出会いも、西里社長が売ることにこだわる要因となった。
西里社長はかつて稲盛氏の著書を読んで感銘を受け、尊敬する経営者として慕っていた。機会あれば本土に出向いて講演なども聴講した。しばらくして稲盛氏が塾長を務める「盛和塾」に縁あって入門することが叶う。
あるとき西里社長は、工場に設備投資して増産する計画を伝えたところ、稲盛氏は「そりゃあんた、売る方が先でしょ」と一刀両断にされた。
雪塩をはじめ商品の売れ行きは好調で、もっと生産量を増やしたいと食い下がったが、「売る方が先。売れに売れて、にっちもさっちもいかない、どうしても間に合わないとなったときに初めて工場を大きくしたらよろしい」という返答だった。

雪塩ミュージアム内のショップ。雪塩を使った美容商品は若い女性にも人気だ
「塾長もメーカー出身の人間なのに、なんで分かってくれないのか……」。西里社長はその場では嘆いたものの、アドバイスに従ってギリギリまで生産量を増やすことをせず、逆に新たなショップを立ち上げるなど、売ることだけに心血を注いだ。そうした環境を作ることで、社員が自ずと売るための工夫をしたり、顧客のニーズを汲み取った提案をしたりするようになった。この経験がパラダイスプランの販売力や営業力の土台となり、島の駅の成功にもつながったのだという。
私利私欲の人間は応援されない
しかし、単に直売所を作ればものが売れるほど簡単ではない。ここで2つ目の心がけ、「地域貢献への意識」が重要になってくる。
沖縄企業が売るために必要なのは、「地域に根ざした事業を展開し、地元の人たち、さらには外の人たちにも応援してもらうこと」だと西里社長は言う。きれいごとのように聞こえるかもしれないが、西里社長は本気だ。

かつてはサトウキビ畑しかない貧しい島だった。これが宮古島の原風景である
「宮古島のために」——。この島で生まれ育った西里社長は、愚直に地域全体の利益を追求している。島の駅みやこも宮古島の生産者を応援したいという一心で立ち上げた。雪塩の商品名に「宮古島」の文字が入っているのも地元に対する気持ちの表れである。
「『宮古島の雪塩』という名前を誇りにして売りたいと思いました。宮古島という言葉があるからこそ商品のイメージが沸くし、応援してくれる人がいるのです。単に『雪塩』だったらここまで応援されることはないですよ」(西里社長)
西里社長はもう一つ付け加える。応援してもらうためには私利私欲に走っては駄目だという。
「僕らがどれだけ儲かるのかなどお客さんは全く興味がありませんし、金儲けばかりするような人間は応援したくないですよね。地元の人が拍手を送るのは、実は商品ではなく、僕らの志に対してです。そういうところにしか共感は生まれません。だから商売というよりも地域を盛り上げる運動に近い観点で物事を考えています。そのために、島の駅でも定期的にイベントをやったり、祭りをやったりして宮古島のものづくりを情報発信しているのです」
島の駅をきっかけに、人気に火がついた商品がメロンである。宮古島のフルーツと言えばマンゴーが有名だが、メロン栽培も盛んなことを知る人は少ないだろう。なぜなら県外にはあまり出荷されていないからだ。けれども、島の駅では珍しさもあって飛ぶように売れている。18年度は約2000万円、19年度は約3500万円を売り上げた。宮古島では二毛作なので、冬場でもメロンが食べられると好評だ。
地元農家の小禄繁さん、ヨシ子さんはもともと、ピーマンやゴーヤーを育てていたが、3年前からメロンを作り始めた。これまではJAにだけ出荷していたが、知人の紹介で島の駅みやこにも卸すようになった。「店の人たちが丁寧にメロンを売り場に並べて、愛情を持って売ってくれるのでとても感謝しています。販促イベントなんかもやってくれるから、お客さんの声も直に聞けて嬉しいですよ」と繁さんは喜ぶ。
こうした地元のサポーターが一丸となって、直売所を盛り上げる。そこに「雪塩」もある。決して、お金儲け一辺倒ではないその志は、消費者の心にも届いているはずだ。

宮古島で20年以上前から農業を営む小禄繁さん(左)とヨシ子さん
徒党を組んで外に対抗する
きちんと顧客にリーチできる売り場を作り、地域に愛される企業になる。これによって沖縄企業の地力は確実に増すだろう。しかし、各社それぞれの努力だけでは不十分だと西里社長は考えている。沖縄資本が強くなり、反撃するためには、沖縄企業が「協調」し、手を取り合って競合と戦うことが不可欠だと西里社長は言う。
「良い意味で徒党を組み、点ではなく面で競合に立ち向かうべきです。そのためにはお互いが刺激し合う関係が大事ですが、沖縄の企業はそれができていません」
政治の世界では「オール沖縄」と声高に叫んでいるが、ビジネスの世界ではそれができていない。個々の企業が県外の強い企業に挑み、撃破されているのが実情だ。ビジネスでもオール沖縄を実現するため、西里社長はオープンな姿勢を貫く。他の経営者、特に若手からの相談を積極的に受けるのも、そのためだ。
「1世代、2世代上の沖縄企業の先輩方にはあまり感心していないんです。結局、人を育ててこなかった。だから沖縄の僕ら40〜50代のビジネスパーソンは誰からも教わってないし、他人に相談することができない中で事業をやっています。この状況を変えていきたい」
「西里イズム」はパラダイスプランの社内にも着実に浸透しつつある。
厳しくてもやるしかない
「宮古島のために、沖縄のために貢献したいという社長の思いは響いています。私は多良間島出身で、いずれ地元に恩返しできる人になりたいと、若い時から思っていました。社長と一緒にこの会社で必死で働いていたら、いつか自分も島に貢献できるのではないかな」
19年7月に入社したばかりの仲間南さん(32)は、こう話す。仲間さんは、当初、沖縄企業にしては、社員のモチベーションが高いことに驚いたと言うが、今では慣れ、西里イズムに食らいついている。逆に、ハードな職場環境だと感じ、辞めてしまう社員も少なくない。それでも西里社長は手を緩めない。

「沖縄が強くなるためには厳しさも必要」と西里社長は力を込める
「沖縄の人たちの甘さはいいところでもあり、悪いところでもあるんです。僕も沖縄で生まれ育ったのでよく分かります。けれど、ビジネスの世界ではそれが裏目に出ている。だったら厳しくてもやるしかないんです」
こう聞くと鬼のようなビジネスリーダーに思えるかもしれない。けれども、等身大の西里社長は気配りの人でもある。毎月、その月に誕生日の社員を集めた会食を欠かさず開いているし、年末には同社の全拠点を行脚して忘年会を開いている。プライベートでは社員と一緒にマラソンレースに出ることもある。
今、コロナ禍で沖縄は苦しい状況にある。だからこそ、西里社長の信念は一層強くなる。沖縄企業の手本になり、沖縄経済をもっと発展させしたい。その揺るぎない目標を達成する日まで全力疾走を止めることはない。
▷第3回:沖縄の貧困の連鎖を断ち切れ 高等教育支援「にじのはし」の志(#3)
▷特集ページ:沖縄チャレンジャー(全4回)
-
地方の企業、行政、地域活性化などの取材を通じた専門性を生かし、「地方創生の推進」に取り組む。1979年生まれ。神奈川県出身。慶應義塾大学環境情報学部卒業、同大学院政策・メディア研究科修了。ニュースサイト「ITmedia」、フリーランスを経て、現在に至る。 |伏見学(ふしみ・まなぶ)