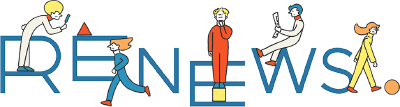鹿児島の秘境でブランド立ち上げ地域おこし 都会キャリアの逆転劇
▷関連記事:「地方創生」5年の成果 脱・東京一極集中、アフターコロナへの期待
鹿児島空港からクルマで約2時間半。大隅半島の端っこにある肝付(きもつき)町・岸良(きしら)という地域をご存じだろうか。人口わずか700人足らず。鹿児島県人でも、どこにあるのかわからない人がいるほどの小さなまちだ。
2019年秋、私はこの地で小さな事業を興した。
「EUDITION(ユーディション)」というブランドを立ち上げ、第一弾として、岸良に古くから自生する地域固有の香酸柑橘「辺塚(へつか)だいだい」を活用した化粧品を開発した。ブランドの目指すビジョンは、「持続可能な地域産業の創出」と「植物多様性の保全」である。

岸良に古くから自生する「辺塚だいだい」(Photo: Yuna Yagi)
私の生まれ育った地元がここだった、という話ではない。鹿児島の出身でも、地方出身者でもない。その対極で、私はずっと都会で生きてきた。
1歳のころから東京のど真ん中で育った私は、慶應義塾大学を卒業後、大手化粧品会社の資生堂に入社。すぐ大阪に転勤となり、関西エリアの百貨店向け法人営業担当となった。
資生堂で約3年勤めた後、英国の大学院への留学を経て、東京のブランドコンサルティング会社、CIAに転職した。プロジェクトマネジャーとして飲食・航空・運送など東京の大手企業を中心に幅広くブランディングのプロジェクトに携わってきた。ずっとコンクリートの上、都会的なビジネスの最前線で朝から夜遅くまでバリバリ働くような人生を送ってきた。

英国の大学院でブランディングを学んだ
そんな私が、縁もゆかりもない鹿児島の、のどかな限界集落で事業をしていると言うと、少し奇妙に聞こえるかもしれない。
ひょんなきっかけで、限界集落の「地域おこし」にかかわることとなり、そこから七転八倒のとんでもない経験を味わい、でも、愛してしまった地域のために自分が成すべきことを悟り、都会のキャリアを生かして事業を起こした、私のストーリー——。
地域おこしの専門家でもない、都会のビジネスパーソンだった私が、少しは地域に貢献できたかと思えるようになるまでのお話に、お付き合いいただきたい。
先輩の軽い誘いに乗って
縁もゆかりもない岸良に惹かれた理由を問われれば、「理屈ではなく五感で魅了された」としか言いようがない。私が初めて岸良のことを知ったのは、ほんの4年ほど前の2016年のこと。それまで、まさか自分が日本の地方、それも限界集落の「地域おこし」にかかわるとは、微塵にも思っていなかった。
きっかけは、16年3月に受け取った1通のLINEメッセージだった。
資生堂時代、上下関係をまったく気にせず付き合える先輩がいた。先輩といっても、私が入社2年目の時に定年退職された歳の離れた大先輩。若手を集めて一緒に飲むのが大好きで、職場の誰からも愛されるような、優しく楽しい人柄のおじちゃんで、私が留学を決めた時も応援してくれ、退職後もやりとりは続いていた。
留学先の英国から帰国してしばらく経ち、コンサルティング会社で朝から晩まで休みなく働いていたころ、不意にその先輩からLINEでメッセージが送られてきた。
「今度、生まれ故郷の岸良で地域おこしのNPO法人を立ち上げるから、開設式においで。海の幸が美味しい、とても田舎でいいところだから」
そんな感じの軽い誘いだったと思う。当時の私は、非常にタフなプロジェクトを担当しており、休日を返上するほど多忙を極めていた。
にもかかわらず、メッセージを受け取った私は、なぜか、本当になぜか、無理やり3連休を取り、岸良に行った。今思えば、コンクリートジャングルの生活に疲れ、心身共に休まる場を求めていたのかもしれない。
日本に残されていた「秘境」
16年3月、まだ肌寒い東京とは違い、春の朗らかな陽気を感じさせる鹿児島に降り立った。方向音痴かつペーパードライバーの私は、空港で借りたレンタカーの頼りないナビで運転するも、旧道に迷い込み、ガードレールも街灯もない山道を死ぬ思いで走った。深い緑に囲まれた道を進むと暗いトンネルがあり、映画「千と千尋の神隠し」の世界に迷い込んだよう。迫りくる山の緑は猛々しいほどに力強いが、しかし、美しくも感じた。
岸良に着くと、とにかく人工的なものが少ないことに驚かされた。緑の青々しさと湿った土と、潮風の香りが混ざった、驚くほど澄んだ空気。そこにあるのは圧倒的な自然の中で、遠慮気味に人が生活するスペースを築いた小さな集落だった。

美しい海岸と、ここで獲れる豊富な魚介類も岸良の魅力だ
パチンコやコンビニ、銀行もない。ガソリンスタンドも週1日だけの営業。ケバケバしい道路沿いの看板も見当たらない。海岸へ向かうと、紺碧の海と誰もいない白い砂浜が存在感を放っている。波は荒いが、海は天然の魚介類の宝庫であり、森に入ると地面や山肌に山菜がそこかしこに顔を出している。
水も素晴らしい。実は上水道が通ったのは18年のこと。それまで住民は豊かで美しい山水で生活していた。まさに秘境という言葉がぴったりで、現代の日本にまだこんな場所があったのかと衝撃を受けたことを覚えている。

岸良の小さな集落。人々がささやかに暮らしている
地域の人もまた、魅力的だった。岸良の人は、鹿児島県人でも分からないほどの謎めいた方言を話し、そして、恐ろしく酒に強い。地域おこしのNPOに顔を出すと、メンバーが熱く盛り上がっていた。平均年齢は65歳くらいだが、皆、垂直に切り立つ岩を長靴でひょいひょい登れるくらい元気な方々だ。
すっかりと岸良の自然と人に魅了された。ただ、それはあくまで「旅行者」としての感覚に過ぎない。それから何度か岸良を訪れては、のんきに美味しいものを食べ、海や川や山を楽しんでいたが、地域をどうこうしようなどと考えることはなかった。
潮目が変わったのは、初めて岸良を訪れてから半年ほどが経った16年夏のこと。先輩とその仲間のメンバーたちから、こう声をかけられたのである。
「辺塚だいだいで特産品をつくりたいからブランディングしてよ。お金ないからタダでね。あと、NPOの理事にもなって」

NPOのメンバーたち
聞く耳をもってくれない地元の人たち
地域おこしのNPOでは、地元の名産品である辺塚だいだいの果汁でジュースや調味料をつくり始めていた。岸良の虜になっていた私は、この申し出を二つ返事で引き受け、まずは課題の整理から始めることにした。
「計画性を持って進めよう。せめてスケジュールを引こう」「取引する人たちとはちゃんと契約を交わそう」
そうした、ビジネスの基本的なアドバイスに加えて、根源的な疑問も投げかけた。辺塚だいだいの生産量は、年間50トンほど。徳島名産のスダチと比較しても10分の1以下であり、地元での消費が中心。県外はもちろん、鹿児島市内に出回ることもほとんどない。
この、少ない生産量の辺塚だいだいから、小さな収益しか生まない加工食品を作ることへの不安を抱いていた私は、「そもそもジュースや調味料が加工品として良いのかもっと議論しよう」とも提案した。しかし、地元の人たちは、なかなか聞く耳を持ってくれない。月1回ペースで、片道7時間くらいかけて東京から岸良を訪れ、顔を見て話をしていたにもかかわらず。
それどころか、前月に来た時には話題にも上がっていなかった商品の容器が、何のテストや検討もなく勝手に決まっていたり、業者とのしがらみで業務発注していたりと、都会の企業のように合理的に物事が進まず、ボランティアとはいえ、大変さを痛感した。
一方で、地域を活性化しようと、皆でああでもないこうでもないと議論しながら、都会では味わえない楽しさも得られていた。国からの助成金もおり、「さあ、いよいよできることが増えそうだ、楽しみになってきた!」と盛り上がっていた17年5月、事件が起きる。
夜逃げ事件
「ごめん」。LINEにそう言い残し、私を岸良に誘ってくれた先輩が夜逃げした。
先輩は、本音を言えば、助成金の予算管理やスケジューリングなど、やりたくはないし、そもそも、できなかった。しかし、周囲には「自分がすべてできる」と大口を叩いてしまっていた。その乖離に耐えられなくなったのだろう。前触れもなく発起人が忽然と姿を消してしまったのだ。
当然、彼を信頼して集まったNPOの仲間たちは打ちひしがれ、男気溢れる強気なNPOの理事長も、この時ばかりは泣きながら電話をかけてきた。私も本当に悔しくて、腹立たしくて、涙よりも、うめき声ばかりが出た。
先輩は口達者で、本当に適当な人だったが、メンバーの心の拠りどころであったことは確か。古い慣習が残るこの地で、メンバー最年長で発起人でもある先輩の言うことは絶対だった。だから、「兄貴が辞めるなら」と他のメンバーも辞めたいと口にする。
とにかく、先輩に戻ってほしい。でないと崩壊する。そう思った私は反射的に先輩に連絡した。
「岸良に戻ってほしい。戻りにくいなら、全部私のせいにしていい。私と喧嘩してちょっと気が動転したとか何とか言えばいいですから!」。そう、電話口で必死に説得をした。
この提案を、私は後に後悔する。先輩は、岸良に戻ったのだが、本当に、素直に、全部私のせいにしたのだ。
「東京から来たあいつ(私)のせいで面倒くさいことになったらしい」。そんな噂が、300世帯ほどの岸良で一瞬にして広まった。それまで優しかった人たちの私への視線は冷ややかなものとなり、身に覚えのないことも言われた。強烈な村八分を体験し、大好きだったはずの場所が一転、地獄のように感じた。悔しくて、思いっきり泣いた。いっそのこと、岸良から永遠に去ろう、とも考えた。
そんなどん底の私を、集落で唯一信じてくれ、救ってくれたのが、NPOの理事長だった。
岸良を後世に残したい
NPOの理事長はくだんの先輩ではなく、無農薬・無化学肥料にこだわって辺塚だいだいを栽培してきた永谷農園の永谷博美さんが務めていた。その永谷理事長と奥さんだけが、悪評が広まった私のことを、以前と変わらず「おかえり」と笑顔で出迎えてくれた。
じつは、永谷理事長は夜逃げした先輩もかばっていた。「もう一度信じて頑張ろう。兄貴を追い詰めた自分たちにも、きっと落ち度があったのだろうから」とNPOの他のメンバーと喧嘩をしてまで、説得していた。なんて寛容で、男気があるのだろうと感動したものだ。

NPOの理事長を務める永谷博美さん
しかし、先輩はまた逃げ出した。あろうことか、二度目の失踪。そして、もう岸良には帰って来なかった。
永谷理事長と先輩は、小さい頃から一緒に育ってきた仲間。永谷理事長は、よそ者の私とは比べ物にならないくらい傷ついたはずで、実際に、傍から見ていて本当に辛そうだった。
このとき、私は岸良の役に立つと心に誓い、覚悟を決めた。他人から見たらちょっと異常な判断に思えるかもしれない。駆り立てたのは、責任感と、地域への強い思いに他ならない。
それまでの、NPOでの商品づくりでは、詰めきれなかったことが山ほどあった。このまま月1回通っていても、何も良いものは生まれない。自分の意思でかかわったのだから、今度は私自身が主体となり、岸良の魅力を伝える商品開発を最後までやりきりたい。そう強く思った。
辺塚だいだいそのものが持つ可能性も私の背中を押した。無農薬・無化学肥料で栽培が可能な、強い柑橘種。植物自らの成分で病気と闘い、環境に適応してきたため、抗酸化作用と抗菌作用があるカテキン類が非常に豊富に含まれており、機能性が高い。
何よりも、「岸良という地域を後世に残したい」という自分の中の思いが、覚悟を決めた最大の理由となった。
岸良地域には、雄大な自然のサイクルがある。日本最大級の照葉樹の原生林に囲まれており、照葉樹は1年を通して落ち葉を堆積させるため、栄養豊かな腐葉土が育まれる。雨が山に降り注ぎ、腐葉土を通って栄養をたっぷり含んだ水が、辺塚だいだいを含む植生と沿岸の海を豊かにしている。
そして岸良は、東京とは異なる社会の仕組みを持つ。取引先に、「簡単でもいいから契約書を作りましょう」と言うと、「相手を信頼しないとダメだ」と全員に笑い飛ばされた。作ったジュースや調味料などの商品はどんどんと人に配り、お礼に何かをもらって満足する。資本主義の競争、契約・貨幣社会といった概念とは一線を画する、少しプリミティブな雰囲気を纏う魅力が、そこにはある。
私を岸良の虜にした、この自然と社会の存在を守りたい。そんな思いが、悲嘆に暮れていた私を駆り立て、奮起させた。と同時に、一連の事件が岸良での活動を振り返る良いきっかけとなり、かかわり方を根底から変えることとなる。
「地域おこし」のハードルを勝手に上げていた
地域にかかわるためには、長期的な視点を持たなければならないし、責任も発生する。かかわる以上、骨をうずめる覚悟で、「中」に入り込まなければいけない……。
そんなことを誰かに言われたわけではない。しかし、それまでの私は「地域おこし」という言葉の意味をそう捉えていた。勝手にそういうものだとハードルを上げてしまい、思い込みに埋もれていた。目的を見失っていた、と言い換えることもできる。
しかし、私はそもそも、地域の課題すべてを解決できる“超人”になりたかったわけでも、岸良の内側に入り込み、「岸良人」になりたかったわけでもない。
私の目的は、岸良を活性化することだったはず。そのために、辺塚だいだいのポテンシャルを最大限に引き出す方法を考え、全国に通用するブランドとして育てる。これが私のやるべきことだと悟り、岸良を守るため、持続可能な産業創出に向けてイチから出直すことにした。
立ち位置を「内」から「外」へ
とはいえ、産業を創るといっても簡単ではない。私自身、地方、しかも岸良のような地域でビジネスを立ち上げるのは初めてのこと。お手本もない中、自分が頼りにできるのは、都会のビジネス現場で培った経験や知見だけだった。だが、この田舎とは無縁、対極にも思える都会流のアプローチが、意外にも奏効するのである。
まず前述の通り意識が変わった私は、岸良の産業創出に向け、どういう体制で臨むべきか、見直した結果、岸良の内側ではなく、外側にチームを作ろうと決めた。
先のエピソードにもあったように、古くからの慣習が色濃く残る岸良では、男性の年長者の言うことが絶対。岸良とのかかわりをもった私は、可愛がってもらったけれども、どこまでいっても「よそ者」であり、女性である事実も変わらない。NPOの理事といっても、マスコット扱いだった。
だから、立ち位置を明確に変えることにした。「内側」から、「外側」へ。内部の協力者から、プロに徹したビジネスパートナーへと。じつはこれは、かつての私の仕事の仕方、そのものと言える。
コンサルティング会社のプロジェクトマネジャーとして私は、さまざまな会社の事業立ち上げなどに携わってきた。プロとして、顧客企業と適度な距離感を保ちながら、しかし、顧客企業とともに同じゴールを目指し、最適な人材を配置したチームを組成し、バリューを発揮する。
考えてみれば、地域活性と言っても、「岸良を活性化させる」というプロジェクトだと思えば、気負うことはないし、内側に入り込む必要もない。私は、東京で立ち上げたスイロという会社の事業として、岸良の活性につながる、辺塚だいだいを用いたブランド開発を推進することにした。
そして、第一弾の商品化として、「化粧品」を選んだ。
あらゆる課題を解決する「化粧品」という解
岸良には名産品がない。だから、辺塚だいだいのジュースなどの加工品を特産品として開発し、販路を拡大し、認知を上げる。というのが、NPOがもともと考えていた地域活性の方法だ。
しかし、販路が拡大できたとして、生産量が足りないという課題に突き当たるのは目に見えていた。仮に植樹などによって辺塚だいだいの生産量を上げたとしても、新たな課題が浮上する。苗木を植え、果実が採れるまで3~5年。その世話を誰がするのか、誰が大量の果実を収穫するのかを考えたとき、負担が増大する農家との軋轢(あつれき)が生じるのは容易に想像できた。
ゴールは岸良の活性化。商材は辺塚だいだい。しかし、生産量はいたずらに増やせない——。この方程式の解が、化粧品だった。
ジュースなどの加工品製造の際に捨てられる果皮と、剪定で切り落とされる枝葉が化粧品の原料となる。果皮と枝葉から抽出した成分は酵母で培養し、増やせるため、少量でも問題はない。さらに果皮と枝葉は冷凍保存が可能なため、収穫量が増減したとしても安定供給できる。
この方法なら、現在の生産量で十分な量の化粧品原料がつくれる上に、すでに取り組んでいるジュースなどの加工品や生鮮品向けの量を取り上げることもない。用途がなく捨てられていたものをアップサイクルするので、農家にとって負担はなく、プラスアルファの収益を提供できる。
かつて働いていたコンサルティング会社でも、顧客企業からの依頼に対して、まったく違う角度からの提案を行うことがあった。例えば、ロゴを変えたいという依頼があったとする。しかし、ロゴを変える背景や、ブランドを取り巻く本質的な課題は何かを読み解き、その課題を解決するために仮説を立てて検討してみると、じつはロゴを変えることに意味はなく、まったく別のことをすべきだという結論に至ることもある。
私は、化粧品原料の開発に挑戦することで、辺塚だいだいを活用して岸良の活性につながる、という仮説にたどり着いたのである。
そうと決まれば、すぐ商談だ。
よそ者のパートナーに徹する
「処分する前提の辺塚だいだいの果皮と枝葉を購入させてほしいです」
まず私は、永谷農園のトップでもあるNPOの永谷理事長にそう伝え、こう熱弁を続けた。「自分の会社で、自分の責任の範囲で、化粧品原料として開発する分には問題ないでしょうし、NPOには迷惑をかけません。開発に成功したら売り上げの1%をNPOにも還元するので活動に役に立ててください。私はそういうカタチで岸良に貢献したいのです」。
情に厚く、非常にウェットな関係が好まれる岸良で、ドライな提案は嫌われるかもしれない。だが、そんな私の心配は杞憂に終わり、永谷理事長は快諾してくれた。築いた信頼関係が崩れることはなく安堵した私は、コンサルティング会社での経験を生かし、プロによるチームを組成する。
外部の会社で取り組む新事業なので、何のしがらみもなく、私が考えるベストメンバーをキャスティングし、現地の「人材不足」という課題も解消することができた。もちろん、地域に雇用を生むため、岸良の人もチームに入れることができれば良かったのだが、最初から理想を追い求めるのはやめ、現実的な体制を組んでいった。
よそ者のパートナーに徹することで、地域に入り込むエネルギーと時間を、開発に振り向けよう。そう割り切ったことが、プロジェクトの推進力へとつながった。
そして19年10月。辺塚だいだいのエッセンスが詰まったフェイスオイル「EUDITION OIL」が世に放たれた。まずは美容液からだが、このブランドは化粧品にこだわっていない。日本のさまざまな地域固有の植生を活用し、順次、ラインナップを充実させていく計画だ。

辺塚だいだいを原料にした新しいブランド商品「EUDITION OIL」(Photo: Yuna Yagi)
世間から環境に配慮した化粧品だという評価をいただき、滑り出しは上々。岸良のNPOの面々や地元の方々からも、「化粧品なんて絶対できんと思ってたけど、大したものだ」といった言葉を頂戴した。岸良が生んだ新しい産業として、EUDITIONは希望となりつつある。
急激な変化を起こしてはならない
一つだけ、都会でのキャリアを反面教師とし、心がけたことがある。細くても良い。長く続けられる持続可能なプロジェクトとすることだ。
本来ブランディングは長期的に取り組むべきこと。しかし、コンサルティング会社におけるプロジェクトは、四半期や半期というタイトなスケジュールで結果を求められることが多かった。新商品や新ブランドを立ち上げ、売り上げが落ちたらまた新商品を出す。しかし岸良にとってこのプロジェクトは、1発打ち上げて終わり、では意味がない。
これは、すべての地域活性プロジェクトにも当てはまると考えている。
大々的なプロモーションで大量の観光客を呼び込んだり、特産品を一気にブレイクさせて前のめりに増産したりすることは、平穏な田舎に混乱をもたらすかもしれない。岸良でそんなことが起きたら、原生林を中心とする生態系に影響を及ぼすかもしれない。住人の平和な生活も一変し、ぎくしゃくする。経済的にも、環境的にも、社会的にも、持続不可能な結末となってしまうだろう。

広大な原生林を守るためにも、持続可能なプロジェクトでなくてはならない(Photo: Yuna Yagi)
だから緩やかに取り組み続けられる、継続できる事業の構築を目指した。移住者がポツリポツリと増えたり、辺塚だいだいの生産者の後継が数人でも地元に戻ってきたり、買い取り価格がわずかに上がったりと、「もう少しだけ」豊かになるための変化で良い。そう考え、続けている。
地域それぞれの個性を生かす
これまで食用品としてしかビジネスの選択肢がなかった辺塚だいだいに、新たな活用方法の可能性を見出せたことは、私にとっても自信につながった。
地域特有の植生は、地域の文化であり、魅力ある個性。岸良の食文化を彩る辺塚だいだいは、一度失われると、復活させるのは困難だろう。大量生産、大量消費時代を経て、日本中同じような野菜や果物が安定的に手に入る今の世の中だからこそ、この岸良という地域の魅力を映し出した地域固有の植生は、生き残るべき価値がある。
これは他の地域でも同じだ。日本は南北に細長く、起伏の激しい地形であり、気候風土もさまざま。一括りに「〇〇県産」や「メイドインジャパン」では語れない多様な文化が存在し、点在する地域一つひとつに魅力と課題があるはず。
だから、私はこれから先、この自信を糧とし、岸良に限らず日本のさまざまな地域の小さな魅力を見つけ、産業創出につなげていきたいと考えている。
私の経験は、必ずしも地域おこしの「答え」ではなく、いろいろな形があって然るべきだと思う。ただ、都会でビジネスキャリアを積んだ一人でも多くの方が、このストーリーをきっかけとして、キャリアを地方のために生かそうと思ってくれたら、幸いだ。
-
1986年徳島市生まれ。慶應義塾大学商学部卒業後、株式会社資生堂入社。英国University of East AngliaにてMSc Brand Leadershipを修了し、CIA Inc.にプロジェクトマネージャーとして参画。2016年株式会社スイロ設立。19年に新ブランド、EUDITIONを立ち上げる。 |岡田麻李(おかだ・まり)