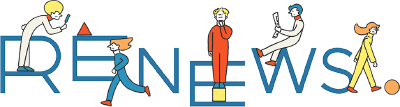オール沖縄で貧困支援を 「地域円卓会議」がもたらす光明 #4
▷第3回:沖縄の貧困の連鎖を断ち切れ 高等教育支援「にじのはし」の志(#3)
34.8%という全国一高い貧困率を示す沖縄県。「貧困」という無視できない現実を直視し、課題解決に立ち向かう「チャレンジャー」を本特集で追いかけてきた。(注:貧困率は、山形大学・戸室健作准教授(当時)が2016年に発表した「都道府県別の貧困率」より)
沖縄初の子ども食堂として2015年に開所した「ももやま子ども食堂」は、運営スタッフに「ナイチャー(本土出身者)」を巻き込むことで、他の施設にはない支援を次々と打ち出してきた。
「雪塩」で有名なパラダイスプランは、県外、あるいは海外の企業にも負けないようにするため、地元企業の連携によって「地場力」を高めるべく奮闘している。
児童養護施設出身者の修学支援を行う「にじのはしファンド」は、世代をまたぐ「貧困の連鎖」を断ち切ることが先決とし、恵まれない子どもを対象に、大学や専門学校など高等教育の機会を提供している。
他にも沖縄の貧困を解決するために日夜奔走する人々や組織はたくさん存在する。例えば、シングルマザーの就労を支援するNPOもあれば、貧困家庭の子どもたちに向けた無料塾を運営する企業もある。むろん、沖縄県をはじめとする行政組織も、解決に欠くことのできない「プレイヤー」だろう。
それぞれ、現場で情熱を持って取り組んでいる尊い活動であり、課題解決に向けた一助であることに疑いの余地はない。しかし、これら解決のためのプレイヤー同士が交わることは少ない。寄付者や支援ボランティア、被支援者などが個々のプレイヤーとつながり、多くの活動はその枠組みの内に閉じている。
点と点がつながり、スクラムを組んで交われば、もっと支援の幅が広がるのでは——。
そんな可能性に賭け、実際にアクションを起こしているチャレンジャーがいる。公益財団法人みらいファンド沖縄の副代表理事を務める平良斗星氏だ。
「一足飛びにデンマークのことを言われても困る」
みらいファンド沖縄は、貧困に限らず沖縄全体の社会課題解決を支援する民間ファンド。「沖縄まちと子ども基金」や「ドネーション・ショップ基金」などを立ち上げ、そこで集めた寄付金を各NPOに配分するなどして、沖縄のさまざまな課題解決に寄与してきた。
このファンド事業とは別に、2011年から「地域円卓会議」という異色の事業運営にも取り組んでいる。「まちづくり」や「子どもの支援」など特定のテーマごとに開催しており、これまで91回を数えた。今では年10回程度のペースとなっている。

19年12月に開かれた、部活動の派遣費負担をテーマにした地域円卓会議の様子
この目的も沖縄全体の社会課題解決ではあるが、そのアプローチがユニークだ。まずは、沖縄各所の地域が抱える個別の課題を「シェア(共有)」し、解決に向けて「議論」することに主眼が置かれている。発起人である平良氏は、立ち上げの経緯をこう語る。
「社会課題の解決をテーマに、国内外の素晴らしい事例を紹介するようなシンポジウムやセミナーは以前からありましたが、自分たち沖縄の課題解決にはふさわしいと思いませんでした。参加者はその場では感動しても、いざ自分の地域に当てはめようとすると、ものすごくハードルが高い。例えば、一足飛びにデンマークのことを言われても困るわけです」
「そんな遠く離れた町の事例を紹介するよりも、『今これで困っているんだけどさ』と、目の前で共有されたことに、いろんな人がアイデアを出し合う形式のほうが、具体的なアクションにつながるはず。そう考え、地域円卓会議を立ち上げました」

みらいファンド沖縄の副代表理事を務める平良斗星氏。地域円卓会議ではファシリテーターとして議論を盛り上げる
課題を取り巻くステークホルダーが一堂に会する
言い換えれば、地域円卓会議とは、沖縄の“駆け込み寺”。特定の課題に向き合うNPOや自治体などが「依頼者」となり、解決したい課題をその会のテーマとして会議に持ち込む。ちなみに、“依頼料”というわけではないが、依頼者がその会の運営資金を拠出するというルールだ。
会議には、その会のテーマに関係するNPOなど各種支援組織の他、行政、学識者、メディア、企業など多様な面々が解決に携わるプレイヤーとして参加する。課題を抱える地域の代表など「被支援者」も列席する。
これら、依頼者・各種プレイヤー・被支援者といった課題のステークホルダーが一堂に会し、依頼者が論点提供者として議論の口火を切る。そして、円卓という言葉が示すように対等な立場で、解決に向けて議論を交わす。
一義的には、解決に向けて課題を共有する場ではあるが、その目的はあくまで、課題解決に向けた「アクション」や、新たな「支援スキーム」を生むこと。成果は、着実に積み上がっている。
地域円卓会議での議論が行政施策に発展
17年9月、「若者の定住と働き方」をテーマとした地域円卓会議が西原町で開催された。琉球大学のキャンパスがある同町は「文教のまち」をコンセプトに掲げ、学生の受け入れに力を入れているが、卒業後、大半の若者が転出してしまうという課題に苛まれている。
これを防ぐにはどうすればいいか。卒業後も若者に住み続けてもらえる町作りはどうあるべきなのか。町役場の担当者や自治体会長、地場企業、地元高校生、そして琉球大学の教授、学生などが議論を交わした。
一般的なシンポジウムやワークショップならばここで満足して終わってしまうことも少なくないが、この地域円卓会議はそうではない。
会議終了後も、同会議に出席した行政や琉球大学、県内の公立大学である名桜大学を中心に議論が継続し、具体的なアクションへとつながった。それが18年7月に締結された「西原町と琉球大学および名桜大学による地域における雇用創出・若者定着に係る協定書」である。
同連携協定は、今年度末までに延べ50人以上の学生が町主催の事業へ参加する、毎年31人以上の卒業生が町内で就職する、といった目標を掲げ、大学と自治体がタッグを組んで推進している。さらに、このアクションを機に、同様の取り組みが南城市やうるま市など12市町村でも進み、沖縄全域で大学と自治体の連携協定が広がった。
企業を巻き込んだ新手の支援スキームも生まれている。
19年1月に開催した、「認知症でも安心して暮らせるまちづくり」をテーマにした会議。宜野湾市と西原町が共同で依頼者となり、解決へ向けたプレイヤーとしては、高齢者医療を専門とする特定医療法人、NTTドコモなどが顔を揃えた。
認知症患者の増加と介護従事者の不足で、患者の見守りなどのケアが難しくなり、家族の負担も増している現状が会議の議論で改めて浮き彫りとなった。地域全体で認知症患者を支える、新たな仕組み作りが喫緊の課題。参加者全員がそう理解し、プロジェクトが動き出した。
その後、NTTドコモに加えて地元のIT企業数社も参画。沖縄県の助成を受け、「認知症患者の見守りプロジェクト」の実証事業が19年度末に宜野湾市でスタートした。具体的には、ICタグを持った高齢者が、受信機とIoT通信機を備えた自動販売機の半径15メートル以内に近づくと、家族などの捜索者に位置情報が送信される仕組みを構築。今年11月20日には第1号機が宜野湾市役所の正面入り口に設置された。今後4年かけて市内400カ所まで広げていく計画だ。

今年11月、宜野湾市役所に設置された認知症患者の見守り自販機(写真提供:宜野湾市)
会議のその場でアクションが生まれる
場合によっては、地域円卓会議のその場で新たなアクションや、支援スキームが“誕生”することもある。
12年6月に開かれた、「災害等の停電時の在宅介護家庭における課題解決のため、どんな協働が可能か」というテーマの会議では、台風で停電した際に人工呼吸器が使えなくなるという課題を、依頼者である難病患者支援のNPO法人アンビシャスが提示。参加者の電気工事業者が「人工呼吸器を動かすだけなら簡易版の発電機を使えばいい。1台1万円程度で作れる」という意見を出すと、「それなら、私たちが責任を持って災害時に困っている人たちに貸し出します」とアンビシャスが宣言。行政も支援すると約束し、一気に解決の方向へと舵が向いた。
那覇市からの補助金を得たアンビシャスは、那覇商工会議所とともに簡易発電機を開発。13年、沖縄県から人工呼吸器用外部バッテリーの貸与事業を受託し、停電時における発電機と人工呼吸器の純正バッテリーの無償提供を開始した。

アンビシャスが貸与しているプロパン式の発電機。家庭で契約するプロパンガスボンベを使用して、連続100時間稼働できるという(写真提供:アンビシャス)
また、17年12月開催の会では、都市部の浦添市に残された貴重な天然ビーチ「カーミージー」の保全をテーマに議論が行われた。依頼者はこれまでカーミージーの自然保護などに取り組んできた自治会。今後どうやってこの海を残していくべきか、そのために必要なルールやガイドラインがないという課題を共有した。
市役所の担当者は、「今後は官民が一緒になってカーミージーの保全や利活用のルールを作りたい」と意気込んだが、どのようなルールを、どう作るのか、誰もアイデアを持ち合わせていなかった。すると、「このままでは掛け声だけで終わってしまう」と危惧した参加者から声が上がり、会議のその場で、ルール作りのための「ワーキングチーム」が結成されたという。
年が明けて18年1月に、ワーキングチーム最初のミーティングが開かれ、会議に参加していた約10人を含む官民のメンバーがルール作りに着手。同年11月に「うらそえ里浜の保全・活用ガイドライン」として市から公式ルールが発表されることとなった。
3回に1回は成果を生む
課題を取り巻くステークホルダーが対等に膝を突き合わせ、課題の現状をシェアし、議論すると何が起きるのか——。解決の「打率」が高まることを、地域円卓会議は示唆している。
同会議を契機に、新たなアクションや支援スキームへとつながった事例はどれほどあるのか。平良氏は、「すべてを捕捉できているわけではない」と前置きした上で、「少なくとも3回に1回は、具体的なアクションや支援につながっていることを把握しています」と話す。
つまり、打率3割3分3厘。これを多いと見るか否かは人によるだろうが、少なくとも筆者は「驚くべき成果」だと捉えている。
ただし、お気づきの方もいるだろうが、これら事例は「地域」や「医療」といった課題にまつわるもの。本特集の本題である「貧困」関連の課題ではない。沖縄の社会課題の中でも、貧困は最も解決のハードルが高いのである。

地域円卓会議の過去実績の一部。このように何度も貧困をテーマに扱ってきた
これまでの地域円卓会議において、貧困にまつわるテーマも数多く取り上げてきた。これを機に支援団体への寄付が集まったり、ボランティアの参加者が増えたりということはあったが、新しいアクションや支援スキームが生まれたことは、ほとんどなかったという。平良氏は、こう語る。
「沖縄の貧困は、沖縄の社会問題の中でも群を抜いて難しい。貧困はイデオロギーが絡む問題で、たとえ正しい施策をしても、世の中に共感を持って受け入れられるとは限りません。全員の共感を得るまで、何十回でも貧困解決に向けた対話を繰り返す必要があると感じています。それくらい大きなテーマです」
だが、「光明」はある。今年、貧困分野でも地域円卓会議を契機とした新たな支援スキームが生まれたのである。家庭の貧しさなどが原因で部活動の遠征に行くことができない小中高生を支援する取り組みだ。
保護者などからの問い合わせが殺到
部活動の派遣費は、島嶼部で形成される沖縄特有の課題と言える。遠征時の交通手段は基本的に飛行機。他の都道府県と比べて移動コストが割高になり、家庭の経済的な理由で遠征を断念せざるを得ない子どもは少なくない。19年12月に開催された「部活動の派遣費用負担」をテーマとした会議では、この課題の実態が多くのステークホルダーに共有された。
依頼者は浦添市PTA連合会会長。解決のプレイヤーとして琉球大学の教授などが参加し、被支援者側からは、浦添中学校教頭や沖縄県中学校体育連盟理事長も列席した。議論が進む中、会議に参加していた離島出身の大学生の発言に、一同が突き動かされた。
「これまで自分のお年玉はすべて遠征費用に使っていました」
まずは、会議を運営する、みらいファンド沖縄自身が動く。翌20年1月、10年以上取引のない休眠預金を活用した、部活動の「派遣遠征費用助成事業」を立ち上げた。加えて、独自に「子ども離島派遣基金」も設立した。
反響は大きかった。保護者や部活動の顧問など、現場で課題に直面する当事者からの問い合わせが殺到。企業支援の呼び水にもなった。県内大手の沖縄電力をはじめ、金銭的な援助をしたいという企業がいくつも名乗りを上げたという。
沖縄県も主体者になろう
沖縄の貧困問題解決に寄与する一歩を踏み出した地域円卓会議。その可能性は大きく広がっている。
「沖縄は、実は子どもの貧困に対しては、一括交付金などの補助金がついており、支援団体もたくさん存在します。しかし、貧困は構造的かつ複雑な問題であり、子どもの食事や学習支援だけでは当然解決しません。大人への支援も必要です。だからこそ、貧困というテーマについては、さまざまなステークホルダーを巻き込む必要があるし、そこに地域円卓会議の価値があると信じてやっています」
平良氏はそう意欲を見せる。課題に対して、ステークホルダーが情報や知恵を持ち寄り、支援のプレイヤーがスクラムを組めば、もっとできることはある。個々の支援活動も重要だが、それらが交わることの重要性も地域円卓会議は教えてくれた。
だが、その「交わりの場」をみらいファンド沖縄だけに頼って良いはずがない。

那覇市の中心部にそびえ立つ沖縄県庁。沖縄の社会課題解決に向けて行政ももっと現場に入り込むことが必要だ
この取り組みをスケールさせるには、行政機関、すなわち県が動くべきではないだろうか。どちらかといえば、これまで県は課題解決に向けて助成金を出すことがメインの役割だった。もちろん、これが無意味だとは言わないが、今後は実動部隊としてどんどん課題の現場に入り込み、沖縄が抱える諸問題の解決のために主体的に関わっていく必要がある。なぜなら、県が動けば、有力企業も含めたより多くのステークホルダーを巻き込むことが可能になるし、議論する課題のテーマもさらに大きくなるだろう。
政治や経済の世界では「オール沖縄」が叫ばれて久しいが、社会課題の中で最も解決が難しい貧困問題にも、沖縄に関わるあらゆる人たちが一枚岩になって取り組むべきだ。皆がこの問題解決に真正面から向き合えるようになれば、いずれ貧困に対する意識の差は縮まり、ただただ沖縄の悲惨さばかりを訴えるような声は消えてなくなるはずだ。
▷特集ページ:沖縄チャレンジャー(全4回)
-
地方の企業、行政、地域活性化などの取材を通じた専門性を生かし、「地方創生の推進」に取り組む。1979年生まれ。神奈川県出身。慶應義塾大学環境情報学部卒業、同大学院政策・メディア研究科修了。ニュースサイト「ITmedia」、フリーランスを経て、現在に至る。 |伏見学(ふしみ・まなぶ)