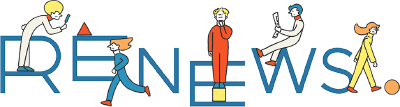沖縄初の子ども食堂 県外の“ナイチャー”が貧困支援で成果 #1
▷特集:沖縄チャレンジャー(全4回)
興味関心はあれども、遠い対岸の地。筆者が初めて沖縄の地を踏んだのは今から9年前。記者となり、しばらく経った2011年3月であった。以降、上辺の沖縄像の向こう側にある「現実」に気づかされることになる。
内地で生まれ育ち、身近に沖縄出身者もいなかった筆者にとって、沖縄に触れる機会はほぼなかった。目を向けさせたのが、1990年代半ばに音楽シーンを席巻した沖縄のアーティストたちだった。「日本なのに日本ではないテイスト」に強く惹かれた。その後、大学で社会学を専攻し、ナショナリズム研究をする過程で、沖縄が持つ文化や歴史、社会の異質性や独自性への関心がより高まっていった。
にもかかわらず、当地を訪れ、現実を見ようとはしなかった。きっかけを与えてくれたのは、沖縄の中小企業の取材。この初訪沖を機に、表層的ではない部分に目を向け、沖縄に対する、ある強い問題意識を抱くようになった。
沖縄経済の今を取材するために繰り返し足を運び、泡盛片手に沖縄の人たちと議論しながら交流を深めた。沖縄や琉球に関する文献も貪るように読んだ。そうした中で、常に「沖縄の貧困」問題が顔を覗かせていたのだ。

ここ十数年の経済成長に反して、沖縄県民の生活水準は低空飛行を続けている。中でも沖縄市やうるま市といった中部エリアは貧困層が多く暮らしていて、さまざまな課題を抱えている
沖縄の発展と裏の顔
1972年に沖縄が返還されて以降、沖縄と本土の格差をなくすため、主に道路建設や港湾整備といったハード面の振興策がとられてきた。1994年からは年間3000億円を超える振興予算が組まれた。一時期は2500億円を下回ったものの、2013年以降は再び3000億円以上の水準となっている。また、2000年のサミット(主要国首脳会議)を境に産業育成などソフト面の強化へと舵を切り、沖縄の経済的自立を進めている。
確かに効果は現れている。
観光収入は18年度に過去最高となる7334億円7700万円を叩き出し、続く「第2の産業」の柱と据える情報通信(IT)産業は、17年の売上高が4361億8900万円と、この20年で3倍以上に増えた。06~16年度の実質経済成長率は平均1.24%と全国トップを誇る。
にもかかわらず、地域にお金が行き届いている実感は乏しく、沖縄の人々の暮らしは一向に良くならない。
16年度の一人当たりの県民所得は約227万円で全国最低。収入が最低生活費を下回る世帯の割合を示す「貧困率」も、山形大学・戸室健作准教授(当時)の16年発表によると、全国平均(18.3%)の2倍近い34.8%に上る。
改めてこの事実を突きつけ、沖縄県民の窮状を訴えることが本稿の目的ではない。インターネットで「沖縄問題」と検索すれば、沖縄の貧困問題自体の指摘や悲惨さを強調した言説で溢れていることが分かるだろう。
一方で現実には、貧しい沖縄の課題解決に向けて奮闘している人たちがいる。筆者は長年にわたる沖訪を通じ、そうした人々や取り組みにスポットライトがなかなか当たらないことに、ある種の歯がゆさを感じていた。
彼ら彼女らこそ、沖縄を良い方向に導く力を秘めている。そんな人々を「沖縄チャレンジャー」と呼びたい。チャレンジャーの挑戦を追い、沖縄社会を好転させる道筋を示す特集。その初回は、沖縄の困窮家庭を下支えする「子ども食堂」に焦点を当てた。
沖縄の支援現場では珍しい“ナイチャー”
沖縄社会は根の深い貧困問題を抱えているが、その根源的な原因の1つが「ウチとソト」の関係にある。沖縄の閉鎖性と、本土の無関心さ、あるいは表面的な問題意識が断絶を生み、解決を遠のかせている。裏を返すと、この状況を変えれば沖縄の貧困は解決へ向かうだろう。
それを体現する場所が沖縄市にある。
那覇空港から高速道路をつたい北へ約40分クルマを走らせ、沖縄南インターチェンジを降りると、広大な米空軍嘉手納基地のフェンスが北側一体の行く手を阻んでいる。その近接地に「ももやま子ども食堂」はあった。

ももやま子ども食堂のある沖縄市は県内でも特殊なエリアだ。市街地の旧名は「コザ」。市の面積の3割以上が米軍基地であり、一人当たり市民所得はうるま市に次いで県内ワースト2の約190万円(16年度)である。加えて、ももやま子ども食堂の対象となるコザおよび山内小・中学校区は、市内16小学校区の中でも就学援助率が高い貧困地域だ
沖縄県には現在190を超える子ども支援施設があるが、ももやま子ども食堂は県内初の子ども食堂として2015年5月5日に誕生した老舗である。
利用者は毎年急増しており、19年度は延べ3059人、単純計算で1日あたり平均8.3人の子どもを支援した。開所からは累計で8000人以上と県内でも有数の規模となっている。そのすべてが困窮した家庭の子ではないだろう。だが、それはほかの子ども食堂も同じこと。つまり、ももやま子ども食堂は、沖縄の貧困問題の解決に一定以上の寄与を果たす、成功モデルと言えよう。実際、ももやま食堂の成功を学びに年間約120人が視察などに訪れているという。
また、今回の新型コロナウイルスの影響によって、県内の6割以上の子ども食堂が休止したり、食事の提供を取りやめたりする中、ももやま子ども食堂は規模を縮小しながらも“居場所”を維持し続けた。食事に関しても弁当の宅配に切り替えるなどし、支援を止めなかった。
県内初の子ども食堂でありがなら、今なお盛り上がりを見せ、結果も出している、ももやま子ども食堂。その成功の要因は「“ナイチャー”の巻き込み」にある。
ナイチャーとは本土出身者を指す沖縄方言。過去を含めてももやま子ども食堂を運営するNPOももやま子ども食堂の職員8人中、3人がナイチャーだ。大学生ボランティアなどを含めるとその割合はさらに高まる。一見、少ない比率に思えるが、沖縄県庁や沖縄市役所の担当部署に尋ねてみると、これだけナイチャー率が高い子ども支援団体は珍しいことなのだという。
現在、NPOももやま子ども食堂の白坂敦子理事長は沖縄出身だが、ももやま子ども食堂を創設したのは東京都荒川区出身の鈴木友一郎副理事長。現場リーダーとして活躍する右腕の菅原耕太氏も千葉県からやって来た人間だ。沖縄に移住して数カ月経ったある日、新聞でももやま子ども食堂のニュース記事を読んですぐ、鈴木副理事長に連絡をとって以来、常勤スタッフとして働いている。
朝ごはんを食べられない子ども
ももやま子ども食堂が発足した経緯を、簡単に説明しておこう。きっかけは、鈴木副理事長の身の回りで起きた出来事だった。
都内の高校から沖縄大学に進学した鈴木副理事長は、卒業して一度は東京に戻ったものの、転職で再び沖縄にやって来た。現在3人の子どもを持つ。2012年、当時小学1年生だった長女が夏休みを迎えた。鈴木夫妻は共働きだったこともあり、長女は学童クラブへ通っていたが、その週は妻も夏休みをもらったため、長女は学童ではなく家で過ごしていた。
すると、長女の友達が朝から家に遊びに来るようになった。友達は長女が朝ごはんを食べ終えるのをじっと待っていた。尋ねてみると、実は朝ごはんを食べていないことが分かった。友達は母子家庭で、母親は夜の勤め。いつも朝は疲れて寝ているため、朝食は出ないという。判明してから数日間は友達も一緒にごはんを食べるようにしたが、妻の仕事が始まり、長女がまた学童へ行くようになれば、難しくなる。この子はどうすればいいのだろうか……。
それ以前から子どもの貧困に問題意識があり、有志で定期的に勉強会を開いていた鈴木副理事長は、「経済的な理由で子どもを学童クラブに預けられない家庭は、沖縄に多い。子ども食堂をやる必要があると痛感した」と振り返る。
思いはあったが資金はない。それから2年あまりが経ち、人づてに喫茶店だった場所を無料で借りることができた。「もう少し準備してからでもいいのでは」という周囲の意見もあったが、「先延ばしにすれば永遠に開所できない」という焦燥感に駆られ、「子どもの日」の15年5月5日、ももやま子ども食堂のオープンにこぎつけた。
沖縄県下で初となる子ども食堂に、問い合わせが殺到。反響の大きさを実感した。中でも嬉しい問い合わせが、千葉出身の菅原氏からのものだった。そのほか、かつてのつてや縁で県外の人たちからも寄付やエールが寄せられた。これが、ももやま子ども食堂の大きな「特徴」となり、成功へとつながっていく。
ナイチャーは「気にしない」
ナイチャーが主力メンバーであると、なぜ上手くいくのか。それは、沖縄特有の強固な人々のつながりや、しがらみを気にすることなく、新たな施策をどんどんと実行していけるからである。
元来、沖縄は地域や人との結び付きがとりわけ強い。それが時には、子ども食堂の活動のボトルネックとなる。周囲の評判を気にするあまり、思うように活動ができず、縮んでしまうこともあるからだ。
そもそも、子どもの貧困支援活動は、閉鎖的になりがち。貧困問題の専門家である湯浅誠氏は、「世間の目を気にして、表立って子ども食堂などとは言わずに支援をしているところも少なくない」と話す。実際、沖縄でも団体数の多さに反して現場からの情報発信が不足しているという声もある。このような閉鎖性は、地域住民のつながりが強固な沖縄で、より顕著となり、沖縄の貧困支援活動の一つの障壁になっていた。

しかし、ももやま食堂は違った。開所当時のことを、現場リーダーの菅原氏はこう振り返る。
「沖縄で馴染みのなかった子ども食堂を県外出身者が急に始めたわけですから、当然、僕らは浮いた存在だったわけです。そもそも、県内初の子ども食堂というだけで、地域の人たちからはいろいろと陰で言われていたと聞きます。でも、直接、言ってくる方もいませんでしたので、そこはあまり気になりませんでした。しがらみがないからこそ、どんどんと先へと進み、新しいことにも取り組むことができました」
新しいこと。その一例が、県内のほかの子ども食堂ではあまり見られない「オープン性」である。
困窮家庭の子どもだけを対象にしているところが多い中、ももやま子ども食堂は週1日、土曜日は参加条件を設けず、どんな子どもでもごはんを食べに来て良いとしている。それどころか、大人も食べて良い。世代を超えた地域交流を図る場として機能している。
「県内のある子ども食堂の運営者たちと話して驚いたのは、皆が口を揃えて『来て欲しい人が集まらない』と言うのです。聞くと、食事もろくに食べられない貧しい子どもだけに利用してほしいとのこと。僕らは貧困だろうが何だろうが、どんな子どもでも受け入れる場所にしたいと思いました」(菅原氏)
これが、どんな利点をもたらすのか。鈴木副理事長がつなぐ。
「ターゲットを絞ったり、クローズドにしたりして、子ども食堂に『困窮』をラベリングしたがる運営者は少なくありません。それによって、『そういう家庭の子が来る場所なんだな』という印象を強めているのです。そうすると保護者も人目を気にして、子どもを預けにくくなり、本当に必要なところへ支援が行き届かなくなります」
地域住民の目を気にせず、困窮家庭や子どもに限定せず、オープンにすることで、逆に本当に困窮した家庭の子を受け入れやすくするという、逆転の発想。しがらみのないナイチャーだったからこそ、気にせず実現できた。
開所から5年経った今でも、「ナイチャーがまた何か新しいことをやっている」と陰口を叩かれることもあるそうだ。けれども、地域や人間関係にしがらみがないため、「いい意味で聞き流せるし、子どもの支援を最優先で考えることができる」(菅原氏)。
もう一つ。「ルールがない」ことも、ももやま子ども食堂の“新しさ”を象徴する。
「貧困の子どもに自立を強いるのは間違っている」
一般的な子ども食堂では、食事の時間が決まっていたり、全員が揃って「いただきます」「ごちそうさま」と挨拶する。しかし、ももやま子ども食堂の子どもたちは、食べたいときにごはんを食べる。そもそも食べない子もいる。実際、筆者が訪れたときも、食事中の子どもの横でカードゲームをする子どもたちがいたり、別の部屋でテレビゲームに興じたりしている子がいた。

平日夜のももやま子ども食堂の様子
とにかく何をしてもいい。勉強しようが、遊ぼうが、強制も干渉もしない。なぜこうしているのか。
「多くの支援施設の場合、子どもに自立を強いるわけですよね。これって変だなと思ってるんです。子どもらしく普通に生きることがまず大切なのに、なぜこういう場所に来る恵まれない子どもには自立を押し付けるのか。僕らは純粋に居場所だけを提供し、こうしなさいとは細かく言いません」と鈴木副理事長は力を込める。
その結果、一度、遊びに来た子どもが「また行きたい」と自ら言うほど、子どもにとって心地の良い場所となり、リピーターが増え、さらなる成果へとつながるという好循環を生んだ。
3兄弟の長男が証明してくれたこと
ももやま食堂は、子どもの「自立」を考えていないわけではない。強いるのではなく、自然と促しているだけであり、方法論が違うに過ぎない。
ももやま子ども食堂は、誰に対してもオープンだ。ボランティアを含めた新しいスタッフにも、視察者や見学者にも常に門戸を開き、県内外の大学や民間企業などからも多くの人が訪れる状況を作り出している。これらによって、子どもたちがより「外の世界」に触れる機会が増え、それが自立へつながると創設者の鈴木副理事長は話す。
「立ち上げ当初は、オープンにし過ぎるのはどうなのかと迷いました。子どもに気を遣わせてしまうのではないかと。でも、杞憂に終わりました。何より、いろんな大人とのふれあいは、子どもの自立を促す。例えば、大学生が気軽にボランティアに来てくれるのは、運営が助かる以上に大事なことなんです。なぜなら子どもたちは自分の“近い未来”をイメージできるからです。イメージすることで、前向きになれる」
ももやま子ども食堂が始まって4年後、嬉しいニュースが飛び込んできた。
ももやま子ども食堂の開始当初から、ある3兄弟が顔を出していた。最初は、運営者が県外ということで訝しがられ、あまり子どもは寄り付かなかったが、3兄弟だけは毎日のように顔を出して食事をとっていた。菅原氏らは、体育館を借りてスポーツをしたり、屋外でイベントを開いたりと、3兄弟がやりたいと思ったことを次々と実現させていった。
そして19年。最初は、小学5年生だった3兄弟の長男が中学3年生となり、自ら率先して、地域のボランティア活動に参加するようになった。きっかけは菅原氏が長男を誘って高齢者を手伝うボランティアに行ったこと。そのときは自宅の窓掃除など1時間程度の作業だったが、帰り際、長男は「楽しかったし、ありがとうと感謝されて嬉しかった」と目を輝かせた。その後も何度かボランティア活動へと足を運ぶ長男が、あるとき学校で表彰されたのである。
これが後押しとなって、長男は人間的にも大きく成長した。今ではももやま子ども食堂にボランティアチームを作り、リーダーとして後輩たちの良い見本となっている。コロナ禍においても市内の訪問介護事業所へ行き、他の子どもとともにマスク作りのボランティア活動に勤しんだ。
「これまで支援されていた子たちが、支援する側に回ったのです」と菅原氏は喜びを噛みしめる。これも、一つの立派な自立。ももやま子ども食堂のやり方が間違っていなかったということを、長男は証明してくれたと言える。彼らの方法論が結果を生んだのだ。
沖縄に急増した子ども食堂
ももやま子ども食堂から火がついた、沖縄の子ども支援。16年度からは内閣府の「沖縄⼦供の貧困緊急対策事業」や、県による「沖縄県子どもの貧困対策計画」が開始し、次々と沖縄に子ども食堂が生まれた。
しかし、その多くは「ウチナンチュー(沖縄の人を示す沖縄方言)」による運営であり、昔ながらのしがらみに縛られているところも少なくない。貧困支援そのものに理解を示さない住民がいる地域では、隠れて運営せざるを得ない施設もあり、中には「施しをしてやると上から目線だったり、補助金目当ての粗悪なものだったりするところもある」(関係者)。
沖縄が抱える子どもの貧困問題についてそれぞれの専門家たちが書いた「沖縄子どもの貧困白書」(かもがわ出版)にもそうしたエピソードが出ている。沖縄タイムス社の田嶋正雄氏によるコラムを以下に引用する。
沖縄県のある街で、2016年、民間団体が運営する子どもの居場所が、オープンからわずか2カ月あまりで閉鎖された。(中略)運営側の代表者やボランティアスタッフが食事を出すだけで、子どもとの関係をつくろうとしていないことが気になった。おとなたちが「施し」の感覚で接しているのも引っかかった。代表者は「近い将来、賞味期限切れで廃棄されるコンビニのおにぎりや弁当を貧困層の子に無料提供するしくみをつくりたい」と語った。貧困家庭の子であることを示すカードを配布して、店で認証できるのだ、と胸を張った。筆者は心のなかで「決して実現しませんように」と祈った。 出典:「沖縄子どもの貧困白書」(かもがわ出版) — 2017/10
もう現場だけでは支えきれない
こうした状況下で、沖縄初の子ども食堂となり、しかも、ナイチャーが主軸となって運営する、ももやま子ども食堂の成果は目をみはるものがある。子ども支援のみならず、沖縄が抱える貧困支援全般への学びは多い。
ただし、順風満帆に見える、ももやま子ども食堂は今、存続に関わるような大きな課題に直面している。キャパシティーが逼迫しているのだ。

ももやま子ども食堂は開所してから3度ほど移転していて、現在は沖縄南インターチェンジのすぐ近くにある
現在利用している施設は、面積・見守りスタッフの面で、子どもの同時受け入れ能力は15人ほどが限界。だが、評判が評判を呼び、ついには50人を超える子どもが集まる日も出てくるようになった。菅原氏は、「これ以上増えたら確実にパンクする」と危機感をあらわにする。
万が一、活動中に子どもたちが怪我などをすれば、一気にバッシングの嵐が吹き荒れることは目に見えている。そうなれば、ももやま子ども食堂の運営を続けていくのは困難になり、沖縄県内の子ども食堂の盛り上がりも下火になるかもしれない。回避するには行政や学校などの協力が不可欠。ももやま子ども食堂は、より広い場所や人材の確保を行政などに訴えているが、なかなか前に進まないという。
「もっと、沖縄の子どものことを、沖縄の社会全体で考えてほしい。行政、民間、地域などそれぞれが役割を果たしていくべきです」
もはや現場の努力の域を超える貢献ステージに入ったと言える、ももやま子ども食堂。この鈴木副理事長の声を、沖縄県民は真剣に受け止めるべきだ。ナイチャーの情熱と知恵と努力を、無駄にしてはならない。
▷第2回:沖縄資本反撃へ 宮古島・パラダイスプラン「雪塩」に学ぶ処方箋 (#2)
▷特集ページ:沖縄チャレンジャー(全4回)
-
地方の企業、行政、地域活性化などの取材を通じた専門性を生かし、「地方創生の推進」に取り組む。1979年生まれ。神奈川県出身。慶應義塾大学環境情報学部卒業、同大学院政策・メディア研究科修了。ニュースサイト「ITmedia」、フリーランスを経て、現在に至る。 |伏見学(ふしみ・まなぶ)